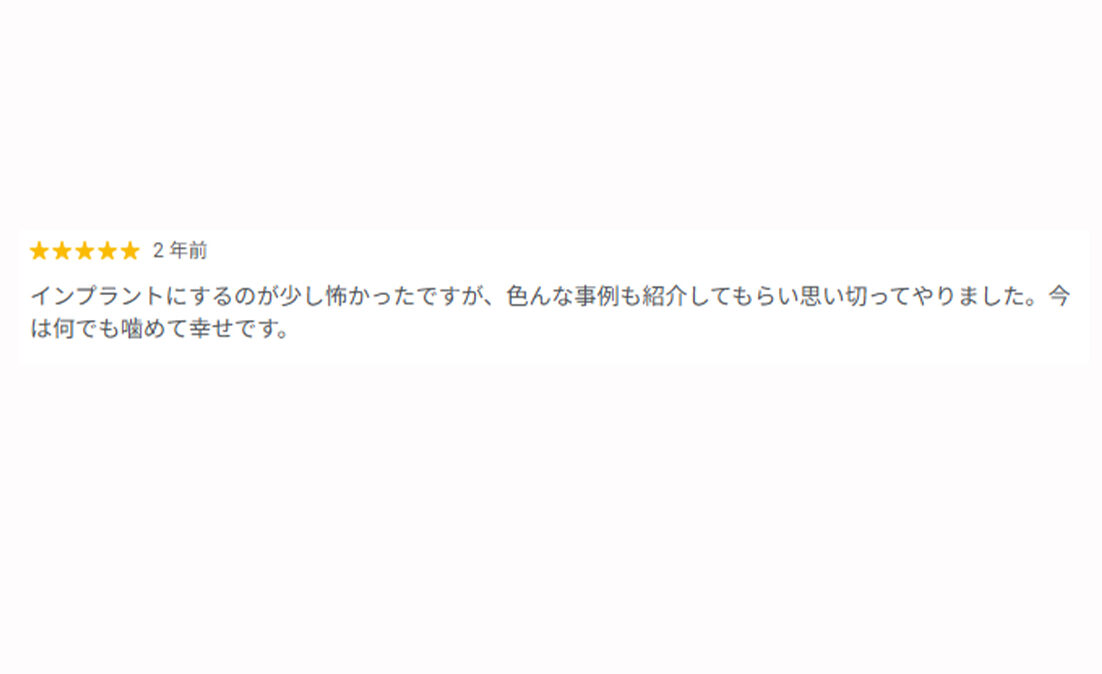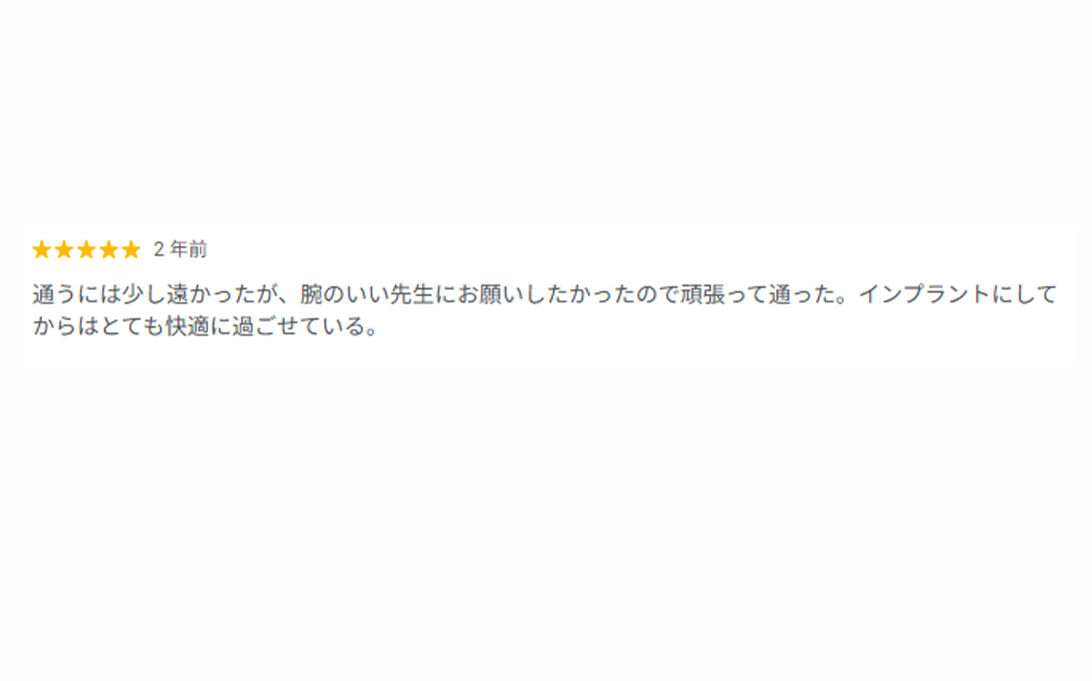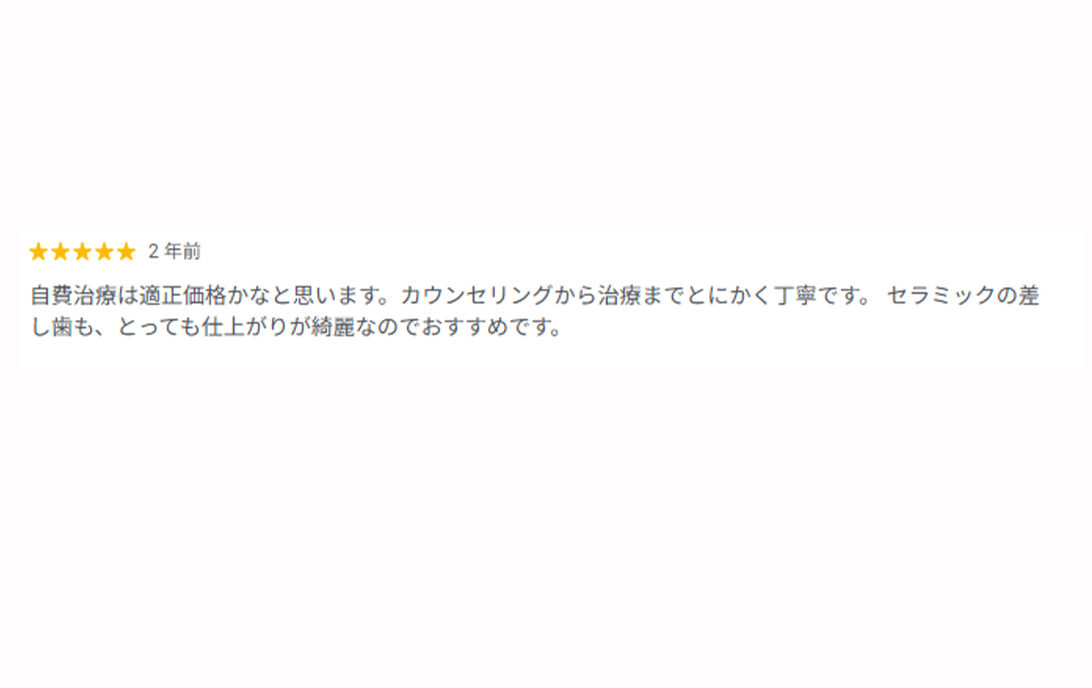歯列矯正は、見た目の改善だけでなく、噛み合わせや虫歯・歯周病リスクの軽減などのメリットがあり、多くの方が注目する治療です。しかし、歯科矯正の費用が高額になりやすいため、不安に感じる方も多いでしょう。特に「歯列矯正には保険が適用されるのか」「公的保険で費用負担を軽減できるのか」といった点は大きな疑問となるでしょう。この記事では、保険が適用される症例や条件、また自費診療の場合の費用対策などをわかりやすく解説します。
歯列矯正に保険は適用されるのか
歯列矯正というと、見た目を良くするための「審美的治療」というイメージが強いかもしれません。実際、厚生労働省の保険診療は、虫歯や歯周病、ケガによる歯の修復といった「病気の治療」が中心で、保険適用が認められています。そのため、通常の歯列矯正は自費診療となり、治療費は全額自己負担が基本です。
ただし、特定の先天性疾患や顎の変形により噛み合わせに機能的な問題がある場合は、保険適用となる場合があります。 これは、見た目ではなく機能回復を目的とした治療と判断されるからです。次に、保険適用の対象となる具体的な症例を確認してみましょう。
保険適用される場合とは?
公的保険が歯列矯正に適用されるのは、「顎変形症」や「先天性疾患に由来する咬合異常」など、機能的な治療が必要とされるケースに限られます。厚生労働省が保険対象と定める主な条件は、大きく分けて以下の3つです。
| 症例区分 | 概要 |
|---|---|
| 先天性異常 | 唇顎口蓋裂やダウン症候群など、厚生労働大臣が定める53疾患が原因で噛み合わせに機能的障害がある場合 |
| 顎変形症 | 上下の顎の骨が大きくずれている、または左右非対称で咀嚼や発音に支障がある場合 |
| 永久歯萌出不全に起因する咬合異常 | 本来生えるはずの永久歯が埋伏したまま、あるいは生えてこないことによる咬合異常が生じる場合 |
これらの症例に該当すれば、保険適用で矯正治療費の一部をカバーできる可能性が高まります。 とはいえ、公的保険が適用されるのは、「顎変形症」や「先天性疾患による咬合異常」など、噛み合わせ機能の回復を目的とする治療だけです。
保険適用になるポイント
顎変形症の場合
「顎変形症(がくへんけいしょう)は、上下の顎の骨の位置や左右差が大きくずれることで噛み合わせが悪化する病気です。原因には遺伝のほか、成長期の癖や外傷なども報告されています。放置すると、顎変形症には以下のようなリスクがあります。
- 咀嚼機能の低下
- 発音・発声への悪影響
- 顎関節症の誘発
- 顔立ちのバランスの崩れ
顎変形症の治療では、矯正治療と顎の骨を切る外科手術(外科的矯正手術)を組み合わせるため、「包括的な外科治療」として保険適用が認められる点が特徴です。具体的には、下顎前突や上顎前突などの顎のズレを改善する手術も併用することで、健康保険が適用されます。
顎変形症の手術を行う医療機関が「顎口腔機能診断施設」に指定されていることは、保険適用の必須条件です。症状が疑われる場合は、まず専門医療機関に相談し、精密検査を受けましょう。
先天性疾患の場合
厚生労働省が指定する先天性疾患や特定疾患が原因で、歯並びや噛み合わせ(咬合異常)に問題がある場合は、矯正治療が保険の対象になることがあります。代表的な例としては、以下のような症候群が挙げられます。
- 唇顎口蓋裂
- ダウン症候群
- ゴールデンハー症候群
また、6~12歳頃に生える永久歯が歯茎に埋まったままの「永久歯萌出不全」では、埋伏した歯を外科的に引き出す処置と矯正が必要になるため、保険適用が認められることもあります。一方、永久歯そのものが存在しない「先天性欠如歯」は、必ずしも保険が適用されるとは限りません。治療方法や判断基準は医療機関によって異なるため、専門医への相談がおすすめです。
保険適用のための医療機関選び
顎変形症や特定疾患による歯列矯正で保険適用を受けるには、厚生労働省の定める施設基準を満たした保険医療機関での診断・治療が必要です。具体的には、地方厚生(支)局に届出をし認可を受けた「矯診(矯正歯科)」「顎診(顎口腔機能診断)」の医療機関にかかる必要があります。
医療機関が公的保険の届け出をしているかは、地方厚生(支)局の公式サイトで確認できます。「施設基準届出受理医療機関名簿」から、お住まいの地域にある「矯診」「顎診」の医療機関を探しましょう。矯正治療は長期に及ぶことが多いので、通院しやすい場所かどうかも考慮しましょう。
保険適用後の費用
保険が適用されると、通常3割の自己負担で矯正治療が受けられるため、自費より大幅なコストダウンが期待できます。例えば総額100万円なら、自己負担は約30万円ほどです。ただし、実際には検査費や入院費、手術費用なども含めたトータルで考える必要があります。
保険診療では、治療ごとに費用が加算される仕組みです。そのため、自費治療のように初回にまとまった費用を払い、あとは追加なしという形にはなりません。治療が長引いて通院回数が増えれば、そのぶん費用もかさむ点には留意してください。
自費診療の歯列矯正費用を抑える方法
歯列矯正は自費診療が基本で、数十万〜百万円単位の費用がかかることも珍しくありません。ただし、以下の制度や支払い方法を活用すれば、負担を軽減できる可能性があります。
医療費控除で税負担を軽減する
医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合、確定申告で所得税や住民税の一部が控除される制度です。歯列矯正が「治療目的」と認められれば、医療費控除の対象となる場合があります。子どもの矯正は、将来的な咬合異常や顎機能の悪化を防ぐ予防的治療と見なされやすく、控除を受けやすい傾向があります。
大人の矯正でも、噛み合わせの改善など治療目的があるなら、医療費控除の申請を検討してください。医療費控除の申告サポートや必要書類の発行に対応する歯科医院もあるため、診療時に確認してみましょう。
分割払い・デンタルローンを利用する
歯科医院によっては、治療費の分割払いに対応している場合があります。クレジットカード払いはもちろん、歯科治療専用のデンタルローンを利用できることも多いです。金利が比較的低めのデンタルローンを利用すれば、高額な矯正治療を分割で支払いやすくなります。
医院独自の分割プランを設けていることもあり、頭金を多く入れて金利手数料を抑える、月々の支払い額を一定にするなど、様々な支払い方法が選べます。気になる方は遠慮なくスタッフに相談してみましょう。
まとめ
歯列矯正は原則、保険の適用外(自費診療)です。ただし、先天性疾患や顎変形症など機能面への悪影響をもたらす症例であれば、健康保険が適用される可能性があります。保険適用の可否は厚生労働省指定の保険医療機関での診断に左右されるため、疑問があれば早めに専門機関へ相談しましょう。一方、保険が効かない矯正治療でも、医療費控除や分割払い、デンタルローンなどを活用すれば費用負担を軽減できます。歯並びの悩みは放置すると、将来的に顎関節症や咀嚼障害、発音障害などを引き起こすリスクが高まります。まずは早めに歯科医院で相談し、自分に合った治療方法を見つけましょう。
静岡歯科では、豊富な治療実績と先端の技術力を活かし、患者さまの希望に沿ったオーダーメイドのインプラント治療を提供しています。専門スタッフのチーム医療と充実したサポート体制で、術前の疑問や不安をしっかりと解消しながら、安全・安心の治療を目指します。まずはお気軽にご相談ください。