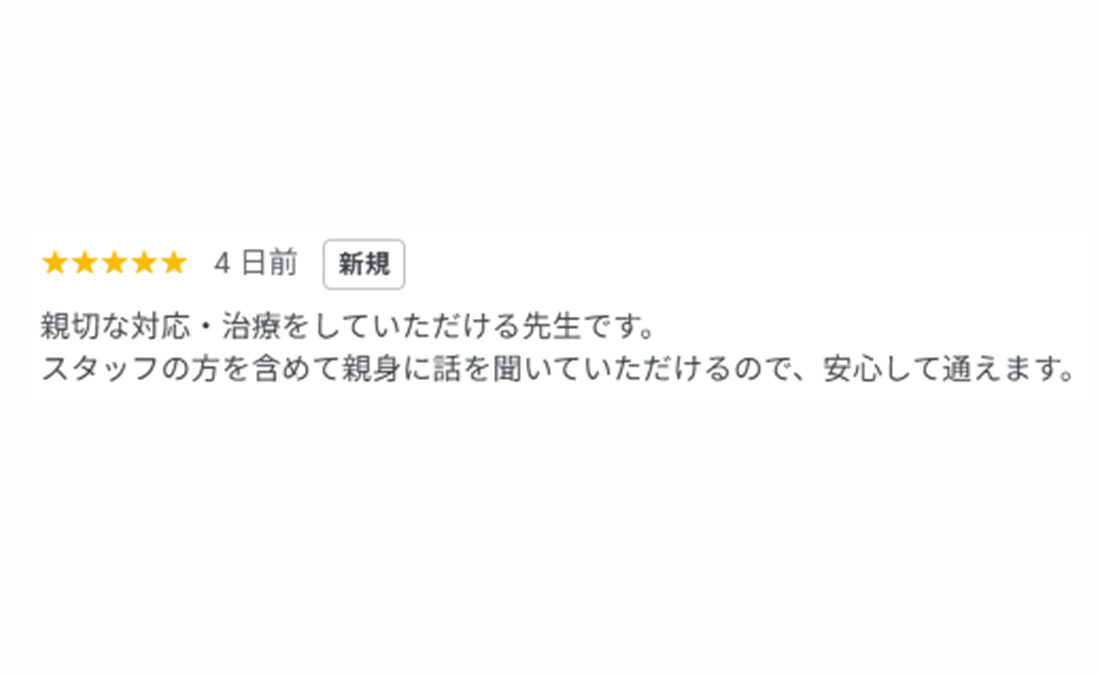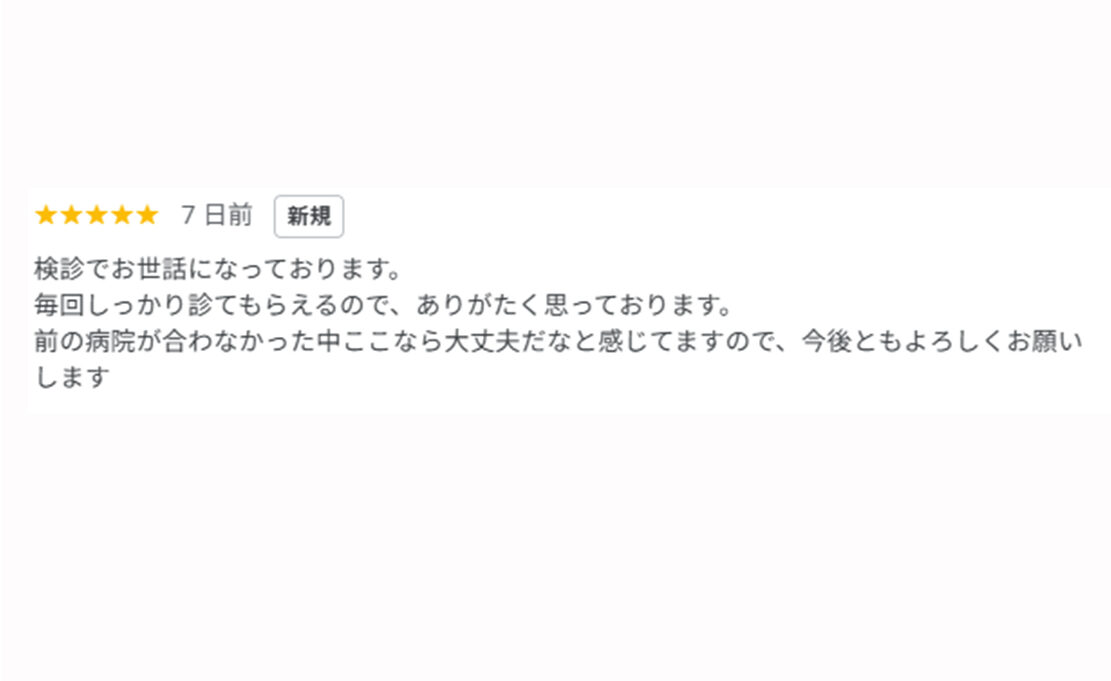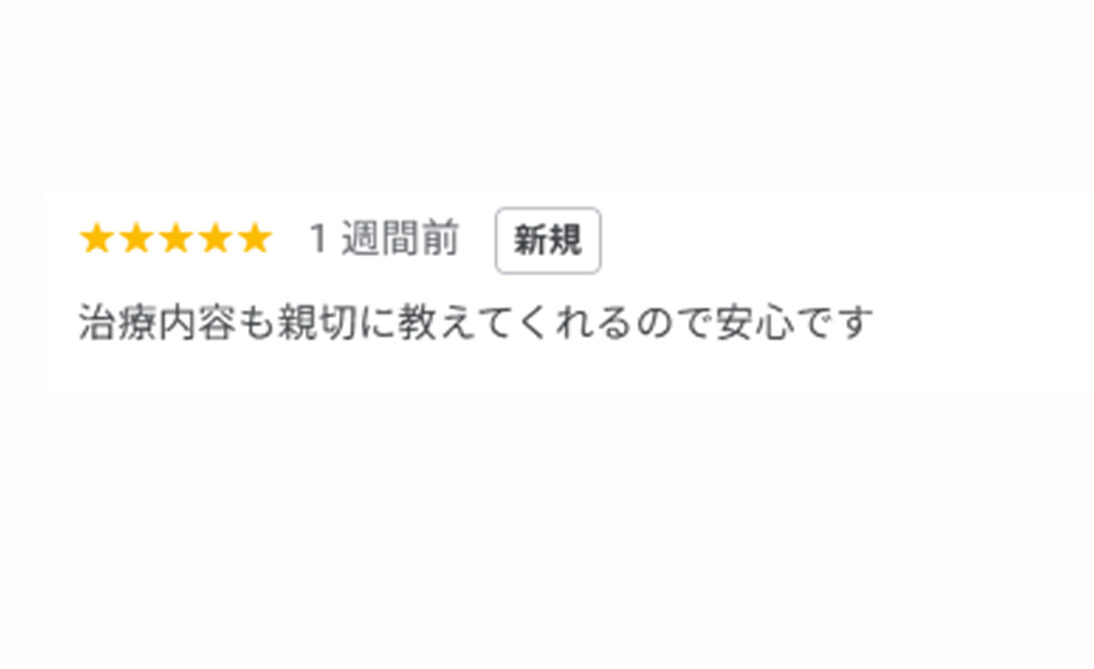歯並びを整えて美しい口元を目指したいけれど、治療期間の長さが気になる……そんなお悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。歯列矯正は、歯を動かして正しい位置に並べるために一定の時間を要します。しかし、人によっては比較的短期間で治療が進むこともあります。
歯列矯正にかかる期間の目安
歯列矯正にかかる期間は、症状の重さや装置の種類、患者さま自身の要素など、さまざまな要因が影響します。ここではまず「全体矯正」と「部分矯正」の大まかな期間の目安について紹介します。
全体矯正の場合
全体矯正とは、上下の歯列全体を動かして噛み合わせや歯並びを調整する治療です。代表的な装置にはマウスピース矯正、ワイヤー矯正、裏側矯正などがあります。平均的には1年~2年半ほどが一般的な治療期間といわれていますが、症例によっては3年近くかかる場合もあります。
| 矯正装置 | 目安の治療期間 |
|---|---|
| マウスピース矯正 | 1~2年 |
| ワイヤー矯正(表側) | 1年半~2年半 |
| 裏側矯正 | 2~3年 |
| ハーフリンガル矯正 | 2~3年 |
矯正期間の長さは症例の難易度や骨格の状態、歯の動きやすさなどで左右されるため、必ずしも上記の期間に当てはまるわけではありません。また、患者さまの協力度合いによっても変動しますので、あくまでも目安として捉えてください。
部分矯正の場合
歯並びが気になる部分のみを集中的に矯正する部分矯正では、3か月~1年程度の治療期間で終わる場合が多いです。全体矯正に比べて短期間で矯正が完了する可能性があるため、前歯のちょっとしたズレを整えたい方や、一部分の歯並びだけが気になる方などに向いています。
| 矯正装置 | 目安の治療期間 |
|---|---|
| マウスピース矯正 | 6か月~1年 |
| ワイヤー矯正(表側) | 3か月~1年 |
| 裏側矯正 | 6か月~2年 |
| ハーフリンガル矯正 | 5か月~1年 |
部分矯正は動かす歯が少ない分、比較的早く治療が終了しやすい点が特徴です。ただし症例によっては部分矯正だけでは理想的な仕上がりにならない場合もあるため、カウンセリングの際に医師とよく相談するとよいでしょう。
歯列矯正で歯が動きやすい人の特徴
歯列矯正の治療期間を短縮させるためには、歯がスムーズに動く状態を作ることが重要です。歯が動きやすい人に共通する特徴と自分の状態と照らし合わせてみてください。
年齢が若い
成長期にある10代の子どもや思春期の若年層の方は、骨がまだ柔軟性に富んでおり、新陳代謝も高いため、歯が移動しやすいとされています。大人になってからの矯正でももちろん歯は動きますが、骨の硬さや代謝の低下などの影響で子どもより時間がかかる傾向にあります。
矯正すべき症状が軽度
歯の重なり具合やズレの度合いが軽度である場合、歯を動かす距離が短くて済むため、スピーディに矯正が進むことが多いです。一方、重度の叢生(そうせい:歯の重なり)や大きな咬み合わせのズレを伴う場合は、長い時間を要する可能性が高くなります。
歯が動くスペースがある
歯列矯正では、歯を移動させるために十分な隙間が必要です。もともと顎が大きい、もしくは歯が小さいなどの理由でスペースにゆとりがある方は、矯正装置の力がスムーズに伝わりやすく、治療期間が短縮しやすいです。逆に顎が小さく歯が大きい場合などは、抜歯が必要になる場合もあります。
舌や口に関わる悪習慣がない
歯ぎしりや食いしばり、舌で歯を押す癖、頬杖など、歯や顎に強い力がかかるような習慣があると、矯正装置が与える力とは別の方向からの圧力が加わり、歯の移動が遅れる原因になります。こういった習慣を改善し、矯正装置にかかる力だけに集中できる環境を整えることも重要です。
新陳代謝がよい
骨の生成と吸収がスムーズに行われるほど、歯は動きやすくなります。スポーツや規則正しい生活習慣で代謝が高い方は、歯列矯正の効果が出やすい傾向にあります。反対に不規則な生活や栄養バランスの乱れなどがあると、骨の代謝が落ちて歯の移動が遅れる可能性があります。
医師の指示を守っている
マウスピース矯正の場合、装着時間や交換タイミングを守ることが大切です。ワイヤー矯正でも、ケアの仕方や食事中の注意事項などを確実に守る必要があります。医師からの指示をしっかり守っている方は治療計画通りに歯が動きやすく、治療期間も短縮しやすいのです。
歯が動きにくい人の特徴
ひとつでも当てはまる場合は、矯正期間が長引く可能性があることを念頭に置きましょう。
矯正すべき症状が重度
歯並びの乱れや噛み合わせの不具合が重度の場合、移動させる距離が長くなるうえ、顎の骨格自体へのアプローチが必要になる場合もあるため、治療期間が長期化しやすくなります。
虫歯や歯周病がある
歯周病で歯を支える骨が弱っている場合は、装置をつけても十分な力をかけづらくなり、歯が動きにくくなります。また、虫歯を治療してから矯正装置を装着する必要があるなど、歯列矯正以外の治療に時間を割く必要があるため、全体の期間が延びる傾向にあります。
噛む力が強い
食いしばりや歯ぎしりの習慣がある方は、強力な力が歯に加わってしまいます。そのため、矯正装置の意図する方向とは別の力が働き、歯が計画通りに動かないことがあります。リラックスするよう心がけ、顎や歯に余分な負担をかけないようにしましょう。
アンキローシスが起こっている
アンキローシスとは、歯と顎の骨が癒着した状態です。外傷や歯周組織の損傷が原因で起こることがあり、アンキローシスになった歯は矯正器具の力が伝わりにくく、ほとんど動かない場合があります。自覚症状がないまま癒着していることもあるため、検査時に医師としっかり相談するとよいでしょう。
医師の指示を守れていない
装置の使用時間を守らない、食事や生活習慣の注意点を守らないなど、自己管理が不十分だと矯正計画が狂いやすく、治療が長引く原因になります。特に取り外し式のマウスピース矯正では装着時間を徹底することが治療成功の鍵です。
医師の技術不足
矯正治療では、医師の経験値や実績が大きく影響します。技術不足の場合はトラブルが頻発し、再調整を繰り返すこともあり、結果的に治療期間が長くなる可能性があります。反対に、豊富な症例を持つ医師であれば、患者さま一人ひとりに合った最適な治療計画を立てやすく、無理のない力加減で歯を着実に動かすことができます。
治療を短期化させる方法
歯が動きやすい人の特徴に当てはまらない場合でも、次のポイントを意識することで治療期間を短縮できる可能性があります。矯正治療中の方やこれから治療を検討している方は、ぜひ取り入れてみてください。
健康的な生活を心がける
骨の代謝を高めるためにも、バランスのよい食事、適度な運動、十分な睡眠を心がけることが大切です。栄養状態が悪かったり睡眠不足が続いたりすると、代謝が低下して歯の動きが遅くなる恐れがあります。規則正しい生活習慣を維持して、身体の内側からスムーズな歯の移動をサポートしましょう。
舌や口の正しい使い方を意識する
舌を前歯に押し付ける癖や食いしばりなどは歯の動きを妨げる大きな要因です。普段から舌の位置や噛み合わせを意識し、悪習慣を改善していくと矯正効果が得やすくなります。医師や歯科衛生士に相談して、正しい舌・口の使い方を学ぶ機会をつくるのもおすすめです。
医師の指示を守りこまめに通院する
矯正装置を適切に装着し、定期的にチェックや調整を行うことで治療期間の短縮を目指せます。マウスピース矯正の場合は装着時間、ワイヤー矯正の場合は定期調整のタイミングを守るなど、医師の指示をしっかり守ることが大切です。少しでも異変を感じたら自己判断せず、早めにクリニックへ相談してください。
実績豊富なクリニックを選ぶ
矯正治療の成功やスピードは、医師やスタッフの実績と経験、そして診療体制に左右される部分が大きいです。多くの症例経験を持つ医院であれば、患者さまのライフスタイルや骨格的特徴に合った治療計画をスムーズに立案してくれるでしょう。クリニック選びの際は、実際にカウンセリングを受けたり、症例数や口コミなども確認してみると安心です。
まとめ
歯列矯正の治療期間は、歯の動きやすさに大きく左右されます。年齢や症状の軽重、口周辺の習慣、新陳代謝の良さなど、さまざまな要因を総合的に考慮しながら、少しでも治療を効率的に進めることが大切です。健康的な生活習慣を意識し、医師の指示を守り、実績あるクリニックを選ぶことで、歯並びを整えるまでの期間を短縮できる可能性があります。
まずは専門家に相談して、自分に合った方法を見つけることから始めてみましょう。日本歯科札幌のクリニックでは、豊富な治療実績と先端の技術力を活かし、患者さまの希望に沿ったオーダーメイドのマウスピース矯正を提供しています。専門スタッフのチーム医療と充実したサポート体制で、術前の疑問や不安をしっかりと解消しながら、安全・安心の治療を目指します。まずはお気軽にご相談ください。