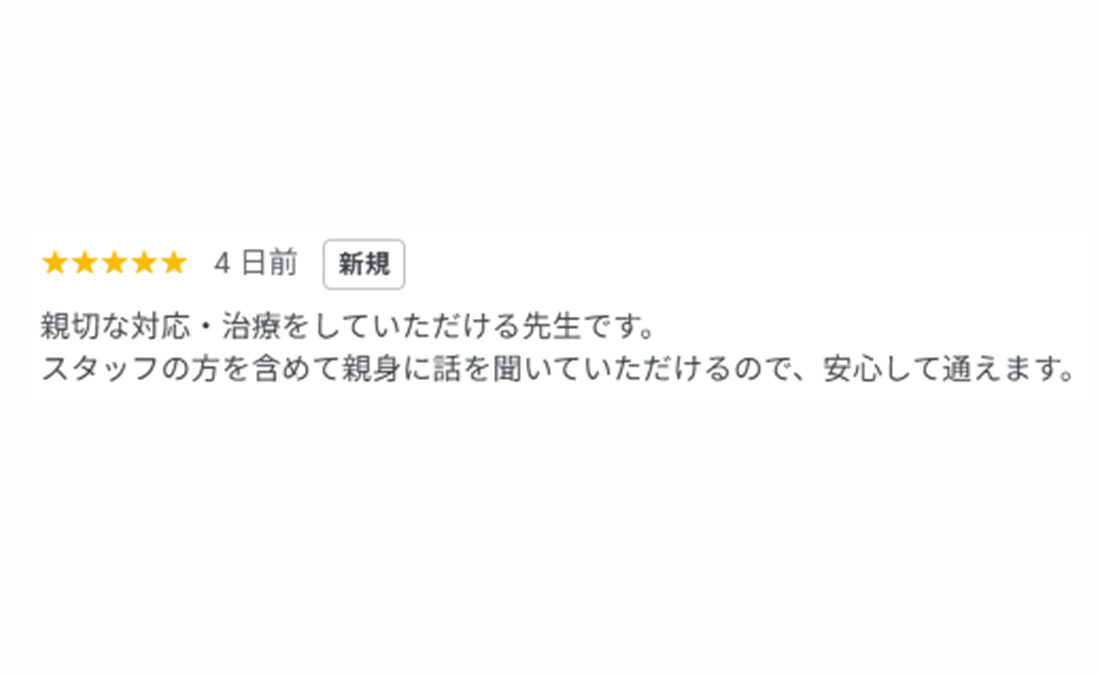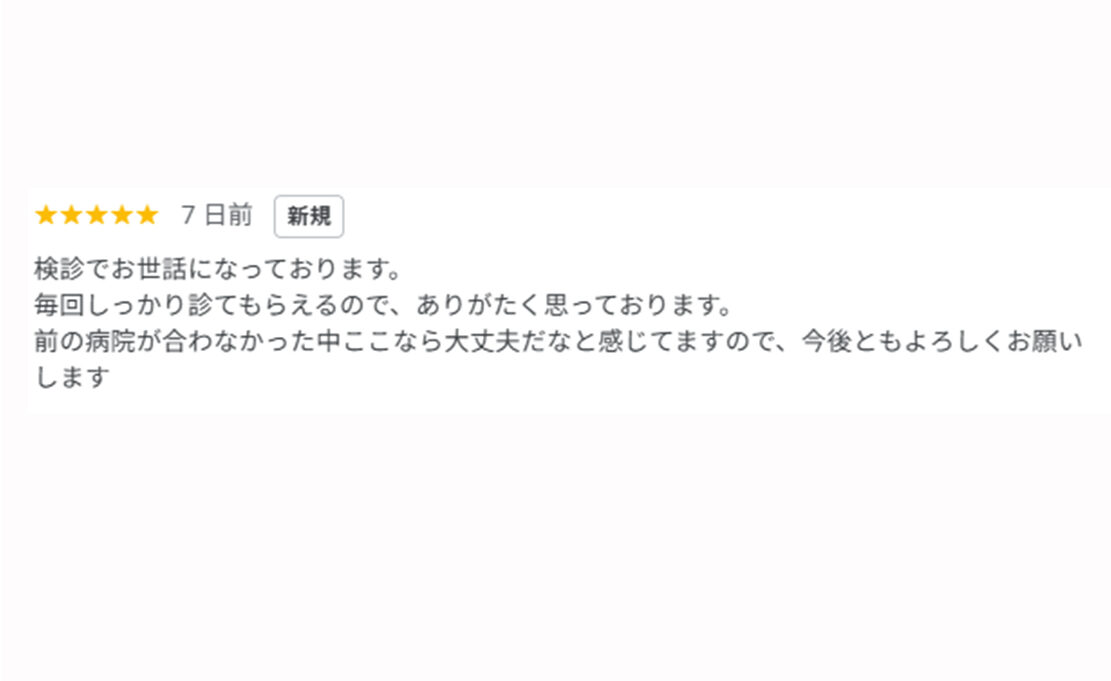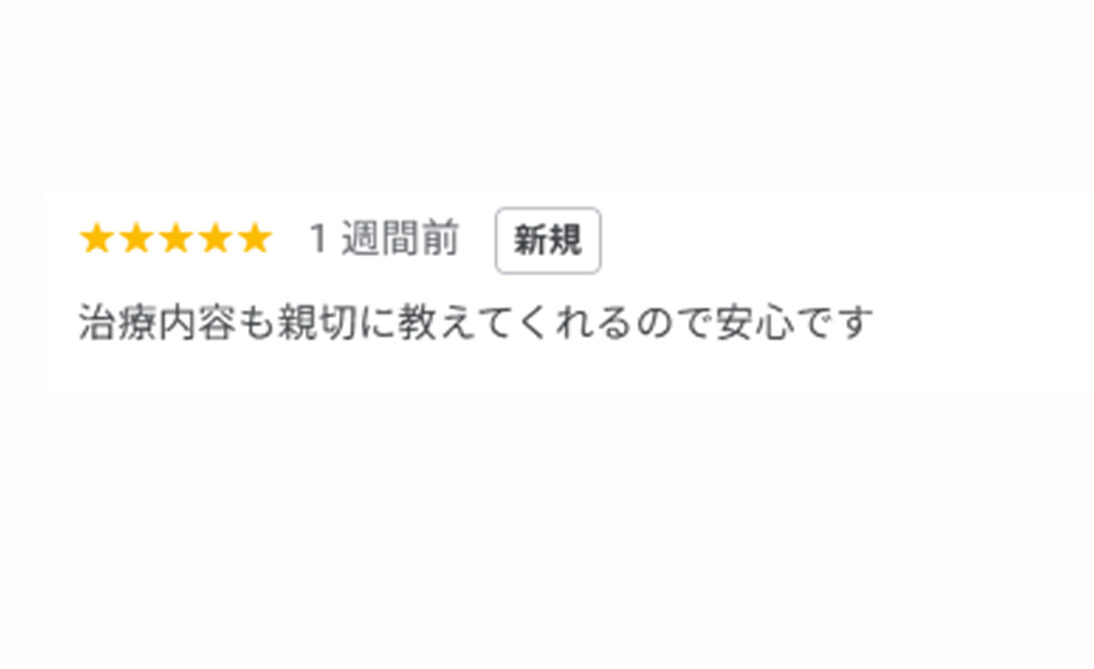歯列矯正をすると、「歯並びをきれいにしたい」「噛み合わせを整えたい」といった理想が実現に近づきます。しかし矯正中は、矯正装置による刺激や負担などから口内炎が発生しやすく、痛みや不快感に悩まされる方も少なくありません。矯正中に起こりがちな口内炎の原因や種類、痛みを和らげるケアや予防法を押さえることで、矯正ライフもより快適なものになります。
矯正中の口内炎ができやすい理由
歯列矯正を始めると、矯正装置の装着や歯の移動に伴う痛みだけでなく、口内炎のトラブルに悩まされることが増える場合があります。実は、矯正中は口内環境が変化しやすいため、口内炎が起こりやすい条件がそろってしまうのです。
矯正装置による物理的刺激
金属ブラケットやワイヤーなどの矯正装置を歯の表面に取り付けると、頬の内側や唇、舌などの粘膜と常に接触するようになります。粘膜は繰り返し擦れて傷つくと、そこに細菌が入り込んで口内炎を発症しがちです。
免疫力の低下やストレス
歯列矯正に伴う食事制限や歯磨きの負担など、生活習慣の変化からストレスを感じやすくなる方もいます。ストレスは自律神経の乱れを招き、免疫力を低下させる原因の一つです。また、矯正中に十分な栄養が摂れない食生活が続くと、ビタミン不足や疲労が重なりやすくなります。これらが口内炎を引き起こしやすい状態をつくり出すのです。
口内炎の原因と種類
そもそも口内炎にはいくつかの種類があり、発生する要因もさまざまです。矯正中に多いのは、物理的刺激が直接きっかけとなるタイプや、免疫力の低下・ストレスからくるタイプです。原因別にみると対策も異なるため、まずは自分の口内炎がどのパターンなのかを把握することが大切です。
カタル性口内炎
カタル性口内炎は矯正装置が粘膜を傷つけた結果、傷口に細菌が入り込んで炎症が起こるものです。矯正装置と歯や唇の動きによって粘膜が物理的に刺激され続け、浅い傷がだんだん悪化するパターンが多くみられます。とくに、歯列矯正を始めた初期はブラケットやワイヤーがまだ慣れず、大きな口内炎ができることもあります。
アフタ性口内炎
アフタ性口内炎はストレスや免疫力の低下、ビタミン不足などが原因で起こることが多いタイプです。小さな白い潰瘍(アフタ)ができ、周囲が赤くただれます。矯正中は不慣れな環境や歯の痛みでストレスを感じやすいことから、このタイプの口内炎を頻繁に繰り返す方も少なくありません。
歯列矯正の種類と口内炎の起こりやすさ
矯正治療にはワイヤー・ブラケット矯正やマウスピース矯正、裏側矯正(リンガル矯正)など、いくつかの方法があります。装置の種類や素材によって、粘膜と装置が接触する頻度や強さが異なるため、口内炎のリスクも変わってきます。
ワイヤー・ブラケット矯正
従来型のワイヤー・ブラケット矯正は、歯の表面にブラケットを装着し、ワイヤーを通して歯を動かします。金属製のブラケットが口内の頬側や唇側に当たるため、初めは特に口内炎を起こしやすいのが特徴です。慣れないうちは「ブラケットにワックスを付けて粘膜への刺激を軽減する」のが有効な対処法となります。
マウスピース矯正
インビザラインをはじめとするマウスピース矯正は、透明のマウスピースを装着して歯を少しずつ動かす方法です。金属アレルギーのリスクが低い、装置が目立ちにくいなどのメリットがあります。マウスピースの縁が粘膜を広い範囲で刺激してしまう場合があり、横に長い形の口内炎ができることもありますが、マウスピースの縁を調整してもらうことで痛みを抑えられます。
痛みを抑えるケア方法
矯正中にできてしまった口内炎は、放置すると痛みが長引くばかりか、食事や会話のたびに強い刺激を伴うことがあります。症状が軽度のうちに対策を取ることで、早めに痛みを和らげることが可能です。矯正中におすすめの口内炎ケア方法をいくつか紹介します。
薬局で購入できる口内炎用の薬を使う
市販の口内炎パッチや軟膏を使うことで、患部を物理的に保護し、刺激を軽減できます。矯正装置が当たって痛みが強い部分に貼る、あるいは塗ることで傷の治りを促進する効果も期待できます。ただし、アレルギーなどがある場合は使用できない成分もあるため、注意書きをよく読んでから使用しましょう。
矯正用ワックスやシリコンを活用する
ワイヤー矯正の方は、歯科医院で配布される矯正用ワックスやシリコンを粘膜が当たる箇所に貼り付けると、口内炎部分への刺激を抑えられます。粘膜との擦れが大きく緩和され、痛みの軽減に役立ちます。ただし、ワックスやシリコンは食事の際に外れてしまう場合があるため、飲み込まないよう注意が必要です。
うがいで殺菌する
口内炎の原因は菌の繁殖にあるため、口腔内の清潔を保つことが何より重要です。歯磨きとあわせて、マウスウォッシュなどを使ったうがいを習慣化しましょう。特に矯正装置を付けている方は、食べかすが装置の間に溜まりやすく、そのまま放置すると細菌が増殖しやすくなります。適切なブラッシングやデンタルフロス、うがいを組み合わせてケアしてください。
口内炎を防ぐための習慣
口内炎は体調や栄養状態とも密接に関係しています。矯正中だからこそ、いつも以上に食事や歯磨きなどの日常習慣を見直し、口内炎の発生を予防する取り組みが大切です。ここでは、毎日の生活で意識したいポイントを詳しくみていきましょう。
バランスの良い食生活
口内炎はビタミン不足が原因で起こることが多いとされています。特にビタミンB2やB6、ビタミンCなどを意識して摂取すると、粘膜の再生や傷の修復をサポートしてくれます。矯正中は歯が痛かったり装置が邪魔になったりで、食べられるものが限られる場合がありますが、できるだけ多彩な食材を組み合わせましょう。以下の表は、ビタミンを豊富に含む食品例です。
| 栄養素 | 代表的な食品例 |
|---|---|
| ビタミンB2 | レバー、牛乳、納豆、卵 |
| ビタミンB6 | マグロ、鮭、バナナ、サツマイモ |
| ビタミンC | みかん、キウイフルーツ、いちご、パプリカ |
硬い食材や粘着性の強い食べ物は、矯正装置を破損させたり外れやすくしたりします。極端に硬い食材は小さく切り分けるか、柔らかく調理してから食べるとよいでしょう。装置に負担をかけず、栄養をバランス良く摂ることが大切です。
質の良い睡眠
忙しい日々や痛みによるストレスで睡眠不足に陥ると、免疫力が低下して口内炎が治りにくくなることがあります。矯正中は「免疫力を保つための睡眠とストレスのコントロールがとくに重要」です。適度な運動や趣味の時間を持ち、心身をリラックスさせる方法を見つけましょう。
正しい歯磨き
矯正装置によって歯磨きが難しくなると、プラークや食べかすが残りやすくなります。雑菌の繁殖を防ぐためにも、矯正用の歯ブラシやタフトブラシなどを用いて細部まで丁寧に磨きましょう。さらに、歯科医院で定期的に検診とクリーニングを受けることで、装置のメンテナンスや口内炎リスクの早期発見・対処が可能になります。
まとめ
矯正中は矯正装置による粘膜への刺激や免疫力低下などが重なり、口内炎ができやすい傾向があります。しかし、適切なケアや生活習慣の工夫で口内炎のリスクはぐっと抑えられます。ブラケットやワイヤーで頬や唇に傷ができる場合は歯科医に相談して調整してもらい、マウスピースの縁が合わないときは早めに処置してもらうことが大切です。
食事では、ビタミンやミネラルを意識して摂取し、なるべく柔らかいものを取り入れるとともに、睡眠やストレス管理にも配慮してみましょう。もし口内炎が頻繁にできたり治りにくかったりするようなら、できるだけ早く歯科医に相談するのがおすすめです。
日本歯科札幌では、豊富な治療実績と先端の技術力を活かし、患者さまの希望に沿ったオーダーメイドのマウスピース矯正を提供しています。専門スタッフのチーム医療と充実したサポート体制で、術前の疑問や不安をしっかりと解消しながら、安全・安心の治療を目指します。まずはお気軽にご相談ください。