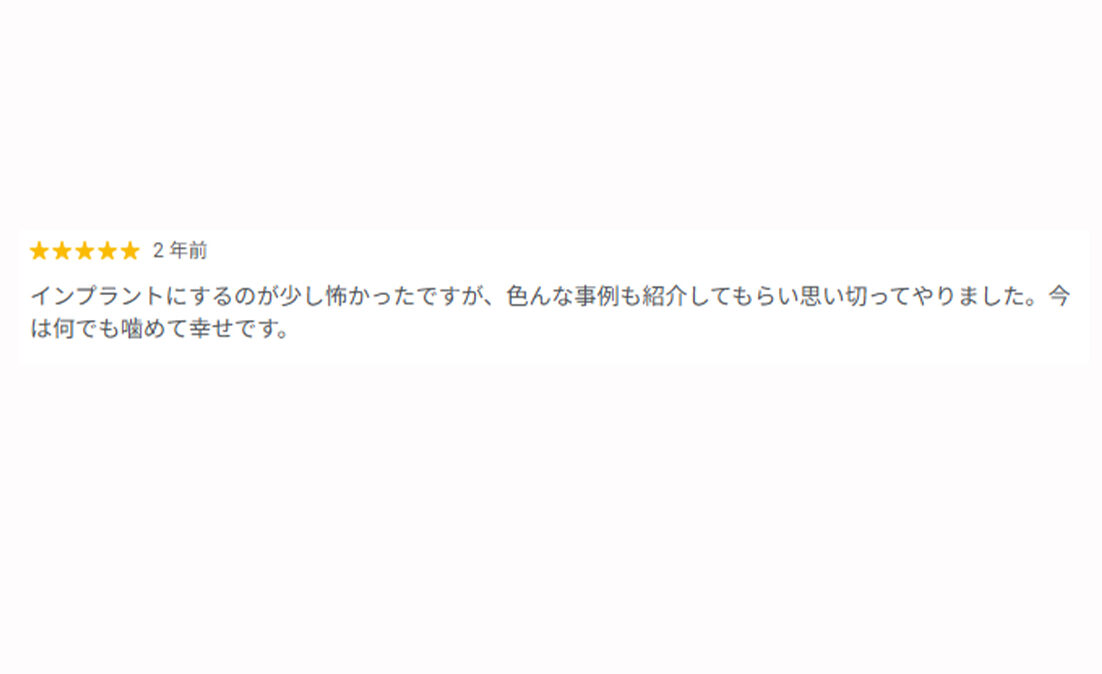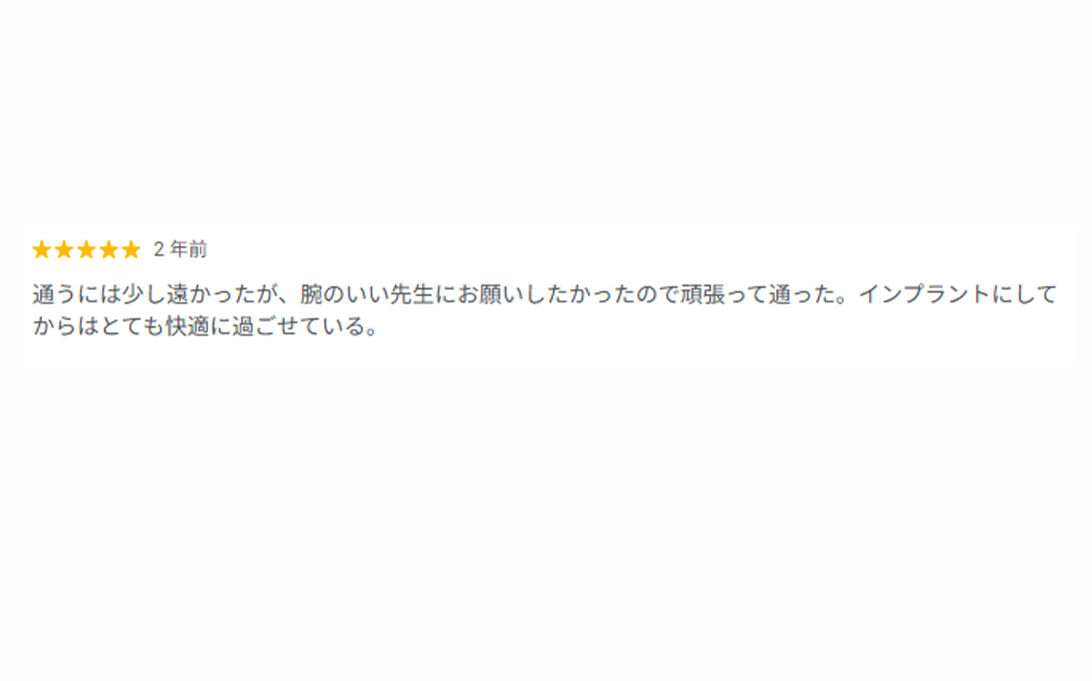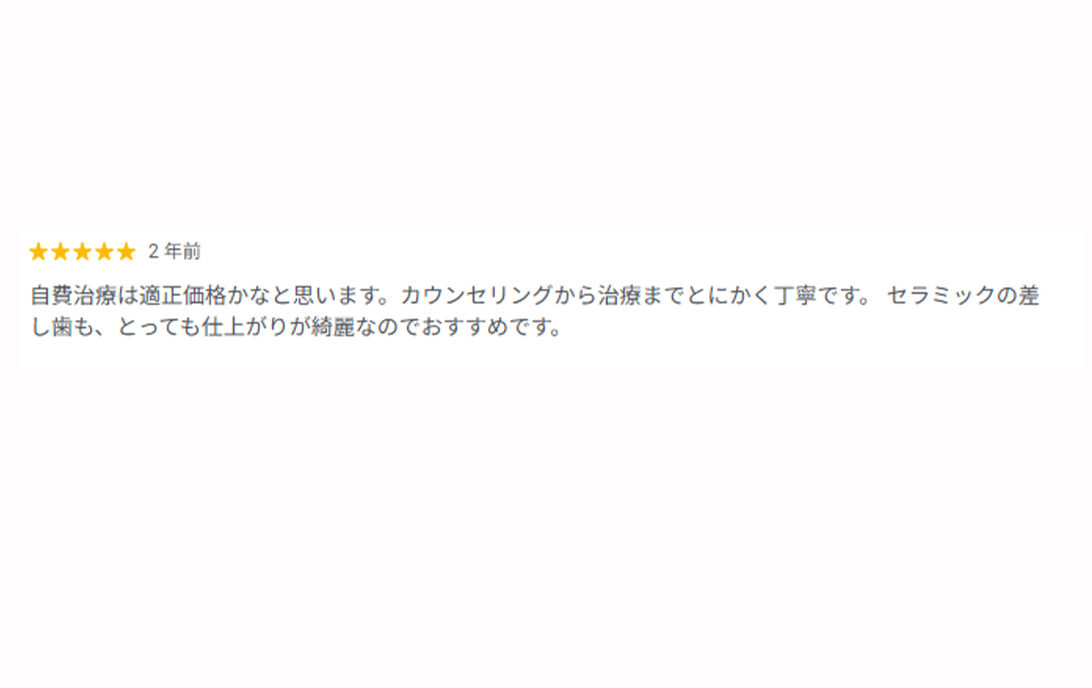「歯並びを整えたいけれど、矯正期間が長すぎるのではないかと心配…」「いつになったら矯正が終わるのだろう…」。こうした悩みを抱えている方は多いのではないでしょうか。
歯科矯正は、見た目のコンプレックスを解消し、機能面でのトラブルを防ぐためにも有効な治療ですが、一定の時間と手間がかかることも事実です。
歯科矯正が長期化しがちな理由
矯正開始前の準備期間が意外と長い
歯科矯正は、カウンセリングを受けてすぐに装置をつけ始められるわけではありません。通常は初回カウンセリングの後、レントゲン撮影や口腔内の検査、歯型の採取など、精密な検査を経て治療計画を立てる必要があります。さらに、必要に応じて抜歯や虫歯・歯周病の治療を先に行う場合もあるため、矯正装置を装着するまでに数ヶ月かかることも珍しくありません。「矯正治療=装置をつける期間」だけだと思っていると、準備の段階でスムーズに進まないことに戸惑い、矯正期間が長すぎると感じてしまう大きな要因となりやすいのです。
歯の移動が少しずつしか行えない
矯正治療では、強い力を一気にかけるのではなく、歯に適切な力をかけ続けることで少しずつ移動させていきます。なぜなら、あごの骨や歯根膜(歯の周囲を取り巻く膜)の代謝サイクルを利用して歯を動かす仕組みになっているからです。特に成人矯正では小児と比べて骨の新陳代謝がゆるやかなため、1ヶ月に0.3〜0.5mmほどしか動かせないこともあります。また、強い力をかけると歯や歯肉にダメージを与え、歯根吸収や歯肉退縮などのリスクが高まる可能性があるため、治療期間を早めたくても安全面から限度があるのです。
「保定期間」を含めると長期間に及ぶ
矯正装置を外して歯並びがきれいに整った後も、後戻りを防ぐために「保定期間」が必要です。後戻りとは、矯正で整えた歯並びが元の位置に戻ってしまう現象を指します。歯槽骨が安定するまでは、リテーナー(保定装置)を装着しておかなければなりません。矯正期間が終わったと思ったらさらにリテーナー装着が数年必要になると聞くと、「いつ終わるの?」と感じてしまう方も多いでしょう。保定期間は少なくとも1~2年、場合によっては10年以上にわたってリテーナーを使い続けることもあります。
矯正期間が長引くケース
重度の不正咬合や骨格的な問題
軽度の歯列不正とは異なり、出っ歯や受け口といった骨格的なズレが大きい場合は、外科的処置が必要になることもあります。その分、時間も労力もかかるため、一般的な1~3年の治療目安よりも長期化しやすいのが特徴です。また、抜歯が複数本必要な場合も移動距離が大きく、必然的に矯正期間は延びる傾向にあります。
担当医の経験不足や不適切な治療計画
歯科医師であれば矯正治療を行うことは可能ですが、歯科矯正は専門性が非常に高い分野です。経験不足や知識不足のまま治療計画を組まれると、診断ミスや装置の選択ミスが生じ、なかなか歯が動かない、装置のトラブルが頻発するなどの問題が起こりがちです。こうした不手際が治療全体を遅らせ、結果として「矯正期間が長すぎる」と感じる原因にも繋がります。
通院ペースの乱れや予約の取りにくさ
ワイヤー矯正をはじめとした矯正装置の多くは、定期的に通院して装置の調整を受けることが必須です。しかし、予約が常に埋まっていて思うように通えない場合や、患者側のスケジュールの都合で通院を先延ばしにし続けると、予定通りに歯を動かせず治療期間が長引きます。特に人気の高いクリニックは予約で埋まりやすいため、キャンセルや予約変更をすると次の予約が数週間後、場合によっては1ヶ月以上先になってしまうこともあるでしょう。
矯正期間をできるだけ短くするポイント
スピード矯正を検討する
近年、歯科矯正の技術や機材は進歩を続けており、従来よりも矯正期間を短縮できる「スピード矯正」という方法があります。
- インプラント矯正:小さなチタン製のネジをあごの骨に埋め込み、そこを固定源にして効率よく歯を動かす手法
- コルチコトミー法:歯槽骨の表面(皮質骨)に傷をつけて骨の代謝を促し、歯を動かしやすくする手法
- 近赤外線を用いた装置:歯槽骨の細胞を活性化し、新陳代謝を高めることで短期的な歯の移動を促進
これらは通常の矯正よりも費用が高額になりやすく、対応できるクリニックも限られますが、症例によっては3~6ヶ月ほどの期間短縮が期待できる場合があります。
歯科医師の指示を守る
矯正治療をスムーズに進めるうえで、もっとも重要なのが歯科医師の指示をしっかりと守ることです。特にマウスピース矯正の場合、1日20時間以上の装着を推奨されることが多いですが、忙しさや違和感から装着時間が足りなくなってしまう場合があります。ワイヤー矯正でも、来院日に装置の調整をきちんと受けられないと計画通りに歯が動かない原因になります。指示や通院スケジュールはできる限り守り、装置にトラブルがあれば早めに連絡することが大切です。
虫歯・歯周病を防ぐ口腔ケアの徹底
矯正装置を装着している間は、装置の周囲に食べかすが溜まりやすく、虫歯や歯周病リスクが高まります。もし治療中に虫歯や歯周病を発症してしまうと、そちらの治療が優先され、矯正計画が大幅に遅れることもあります。歯間ブラシやデンタルフロスを併用して丁寧に磨くなど、日頃の口腔ケアを徹底し、定期的に歯科医院でプロフェッショナルケアも受けるよう心がけてください。
舌や口周りの癖を改善する
舌で前歯を押す、頬杖をよくつく、唇を噛むなどの癖は、矯正に悪影響を与えることがあります。せっかく歯をきれいに動かしても、こうした癖があると歯に余計な力がかかったり、歯が動く方向が妨げられたりするからです。自分だけで癖を意識して直すのは難しいと感じる場合は、MFT(口腔筋機能療法)などの専門的なトレーニングを取り入れている歯科医院を探してみるのもよいでしょう。
信頼できる歯科医院・歯科医師を選ぶ
矯正期間を短く、また適正な範囲で終わらせるためには、適切な治療計画を立てられる歯科医院を選ぶことが大切です。以下のような視点をもとに探すとよいでしょう。
- 矯正歯科治療の実績が豊富な歯科医師が在籍している
- 治療のメリットだけでなくデメリットも具体的に説明してくれる
- 通院スケジュールが柔軟で、予約が取りやすい
- 診断や治療計画がわかりやすく、相談や質問にしっかり答えてくれる
歯科矯正は大きな投資です。カウンセリングや説明時点で疑問を解消でき、信頼関係を築けるかを見極めたうえで、納得できる選択してください。
矯正期間の目安
矯正が長引く原因はさまざまですが、あらかじめ目安となる治療期間を知っておくと、計画的に進めやすいでしょう。
| 矯正方法 | 部分矯正 | 全体矯正 |
|---|---|---|
| マウスピース矯正 | 約2ヶ月〜1年 | 約1〜3年 |
| ワイヤー矯正(表側) | 約2ヶ月〜1年 | 約1〜3年 |
| ワイヤー矯正(裏側) | 約5ヶ月〜1年 | 約2〜3年 |
| 外科手術併用矯正 | - | 約2〜4年 |
これらはあくまで目安であり、個人の歯並びや骨格、年齢によって大きく変わる可能性があります。いずれにしても、安全に歯を動かすには一定の時間が必要な点を念頭に置いておきましょう。
まとめ
歯科矯正は、装置をつけて歯を動かす期間に加えて準備や保定期間があるため、「矯正期間が長すぎる」と感じることもあります。重度の不正咬合や担当医の治療方針、予約の取りにくさなど、複数の要因が重なると期間がさらに長期化してしまうこともあります。もし現在矯正中で進捗が思わしくない場合は、まずは担当医に原因を確認することが大切です。必要に応じてスピード矯正の導入やセカンドオピニオンを検討してみるのも良い選択肢でしょう。
静岡歯科では、豊富な治療実績と先端の技術力を活かし、患者さまの希望に沿ったオーダーメイドのマウスピース矯正を提供しています。専門スタッフのチーム医療と充実したサポート体制で、術前の疑問や不安をしっかりと解消しながら、安全・安心の治療を目指します。まずはお気軽にご相談ください。