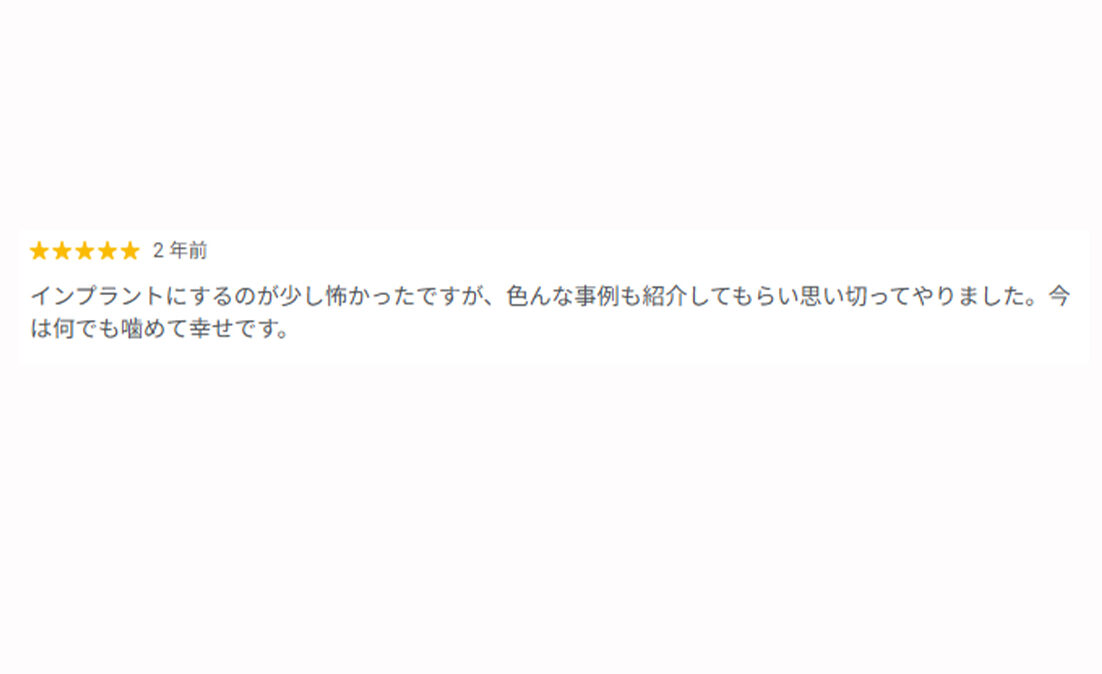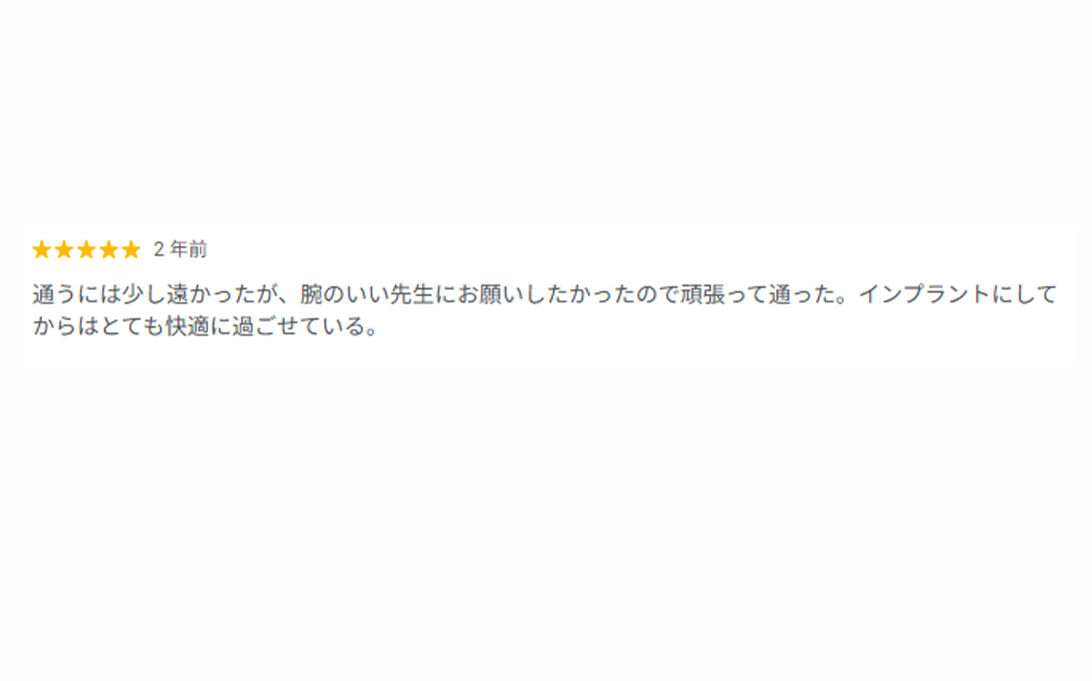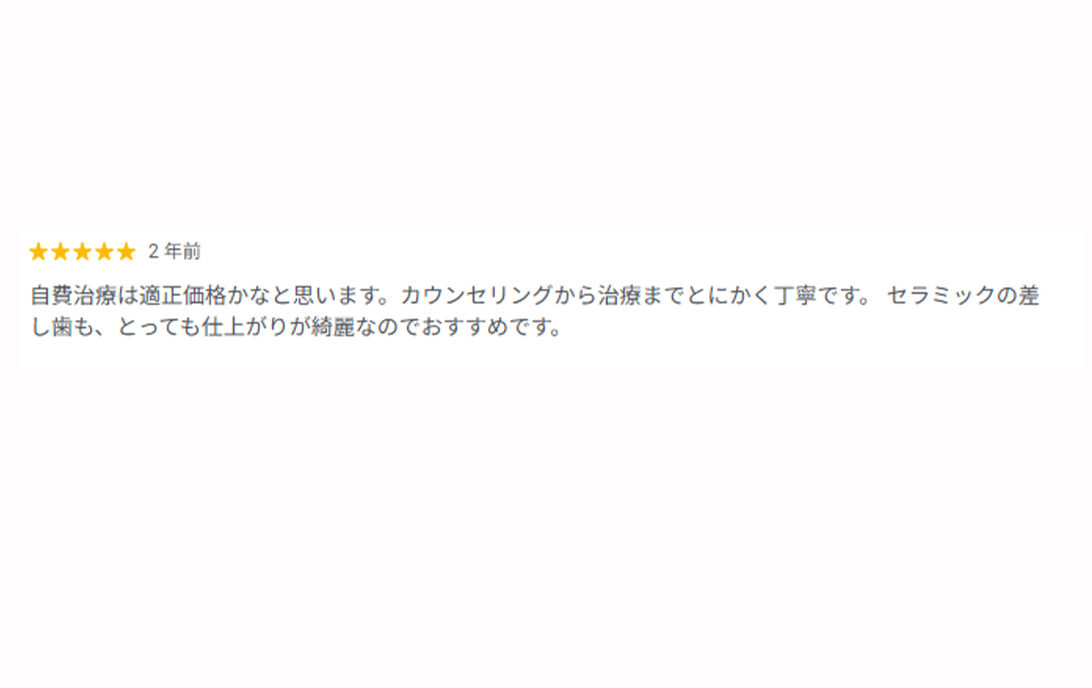矯正治療を検討するとき、口の中にある親知らずを抜くべきかどうかは多くの方が気になるポイントではないでしょうか。奥歯のさらに奥に生える親知らずについて、抜くべきかそのままで問題ないか迷うケースが多いです。実際、親知らずの状態は人それぞれで、生える方向やトラブルの有無によって対応が異なります。本記事では、矯正治療前に親知らずを抜歯すべきタイミングや判断基準、さらに抜くことで得られるメリット・デメリットを詳しく解説します。矯正治療をスムーズに進めるための参考にしてみてください。
矯正前に気になる親知らずの存在
矯正治療前に親知らずを抜歯すべきかどうかは、多くの方が悩むポイントです。親知らずは第三大臼歯とも呼ばれ、一般的には10代後半から20代前半に生えてきます。ただし、生えないまま一生を終える人や、4本すべてがきれいに生える人もおり、その状態は個人差が大きいです。ここでは、まず親知らずの特徴を説明し、矯正治療において抜歯が本当に必要かどうかを考えてみましょう。
親知らずの基本的な特徴
親知らずは前歯から数えて8番目に位置し、上下左右合わせて最大4本まで生えることがあります。しかし、顎の大きさや遺伝的な要因により生えない人もいれば、部分的にしか歯茎から頭を出していないケースもあります。横向きや斜めに生える場合、隣の歯を押し続けることで痛みや腫れの原因となることが多いため、注意が必要です。また、歯ブラシが届きにくい場所にあるため、虫歯や歯周病リスクが高まる傾向にあります。
親知らずは必ず抜歯が必要なのか?
矯正治療においては、すべての親知らずを抜かなければならないわけではありません。以下のような状況であれば、抜歯を回避できることもあります。
- まっすぐに生えており、完全に埋まっていてトラブルがない
- 口腔内の衛生管理が問題なく行われ、むし歯や歯周病のリスクが低い
- 矯正計画上、親知らずが歯並びに大きな影響を与えない
一方、横向きや斜めに生えるなどで今後トラブルを起こす可能性が高い場合や、歯並びを改善するためにスペースを確保する必要がある場合、抜歯が必要になることがあります。つまり、親知らずの抜歯は状況によって判断が異なり、一概に「必ず抜いたほうがよい」というものではありません。
抜歯が推奨されるケース
親知らずを抜くべきかどうかは、次のような要因によって決まります。矯正の専門医や口腔外科医に相談し、事前に十分な検査を受けることで、最適な判断ができます。
親知らずが隣の歯を押している場合
横や斜めに生えた親知らずが、7番目の大臼歯を圧迫しているケースは注意が必要です。こうした状況を放置すると、歯並びが乱れるだけでなく、隣の歯との間に汚れがたまりやすく、虫歯や歯周病のリスクが高まります。とくに矯正治療で歯列を整えようとしている場合、親知らずの影響でせっかく動かした歯が再び乱れる可能性もあるのです。矯正後の後戻りを防ぐためにも、こうしたケースでは抜歯が勧められます。
スペース不足による歯列乱れを防ぐ場合
矯正治療で歯を後方に移動させる際、十分なスペースがないと、治療が長引いたり、歯が思うように動かないことがあります。奥歯が動くスペースを確保するために、矯正前に親知らずを抜く決断をすることがあります。
既に親知らず周辺にトラブルが起きている場合
親知らずの頭が一部しか出ていない場合や歯肉に覆われている場合、汚れが溜まりやすく、虫歯や歯周病などのトラブルを引き起こす可能性があります。これらの問題が顕在化している場合、矯正治療に先立って抜歯を行うことで、口腔内の衛生状態を整えることが望ましいです。
親知らずを抜くメリットとデメリット
矯正治療前後に親知らずを抜くことには、もちろんメリットとデメリットが存在します。以下のようなポイントを踏まえ、自分の状況に最適な判断をすることが大切です。
| メリット | デメリット |
|
|
矯正歯科で親知らずを抜歯できるのか
矯正歯科は歯並びを整える治療の専門クリニックであり、必ずしも親知らずの抜歯に対応しているわけではありません。まっすぐ生えていて簡単に抜歯できる場合は、矯正歯科で処置できることもありますが、多くの場合、口腔外科に紹介されます。
難易度の高い抜歯は口腔外科へ紹介
埋伏している場合や歯根が大きく曲がっているなど、親知らずの抜歯が難しい場合は、口腔外科に紹介されることが一般的です。これは、抜歯時のリスクを最小限に抑えるためです。下顎の親知らずでは、顎の神経に近接していることが多く、慎重な抜歯が求められます。
矯正治療に伴う抜歯費用は保険外が基本
歯列矯正自体が保険適用となるのは、一部の医科歯科連携を行う特殊疾患に限られ、大半の場合は自由診療です。それに伴う抜歯も保険適用外となることが多いため、1本あたり数万円の費用がかかる場合があります。抜歯費用がどのような形で請求されるのか、治療計画の段階で確認しておくと安心です。
親知らず抜歯後の矯正治療の流れ
親知らずの抜歯をすべきかどうかは、精密検査やカウンセリングの結果で決まります。ここでは、抜歯が必要になった場合の大まかな流れをご紹介します。
精密検査・カウンセリング
レントゲンやCTを用いて、親知らずがどのような方向に埋まっているか、または周囲にどんな影響が出ているのかを詳しく調べます。そのうえで、矯正医が矯正プランを立てる過程で「どのタイミングで親知らずを抜くべきか」を判断します。
抜歯後に期間をおいて矯正を開始
抜歯後は、歯茎の穴が塞がり、腫れや痛みが落ち着くまでしばらく待つのが一般的です。通常は1~4週間程度で落ち着きますが、個人差があります。完全に治癒しないまま矯正装置を取り付けると、装置のメンテナンスがしにくくなるなどのデメリットが生じます。焦らず、適切なタイミングを見極めることが重要です。
矯正装置の装着・調整
矯正装置(ブラケットやマウスピースなど)を装着後は、定期的に通院し、歯並びの変化を確認・調整していきます。親知らずを抜いてスペースが十分に確保されていれば、スムーズに歯が動きやすくなるので、全体的な治療期間が短くなる可能性もあります。
矯正治療前に親知らずを抜歯するか迷ったら
「抜いたほうが良いのか、そのままにしても大丈夫なのか」といった親知らずに関する悩みを一人で抱え込む必要はありません。矯正専門の歯科や口腔外科を訪ねて、専門家の意見を仰ぐのが得策です。また、セカンドオピニオンとして別の歯科医の見解を聞いてみることも有効です。
- レントゲンやCT撮影など精密検査で親知らずの位置や形態を把握する
- 虫歯・歯周病のリスクや将来的な歯の動き方を総合的に判断する
- 矯正専門医と口腔外科の連携があるクリニックを選ぶ
特に歯列矯正は長期にわたる治療ですので、最初にしっかりとしたカウンセリングと検査を受け、納得のいく計画を立てることが成功のポイントとなります。
まとめ
矯正治療を始める前に親知らずを抜くべきかどうかは、歯並びや親知らずの生え方、虫歯や歯周病リスクなどを総合的に考慮して判断されます。口腔内の状況によっては抜かずに矯正が可能な場合もありますし、トラブル防止やスペース確保のために抜歯が推奨されることもあります。重要なのは、信頼できる歯科医や口腔外科医に十分な検査と診断をしてもらい、自分に最適な矯正プランを見つけることです。
静岡歯科では、豊富な治療実績と先端の技術力を活かし、患者さまの希望に沿ったオーダーメイドのマウスピース矯正を提供しています。専門スタッフのチーム医療と充実したサポート体制で、術前の疑問や不安をしっかりと解消しながら、安全・安心の治療を目指します。まずはお気軽にご相談ください。