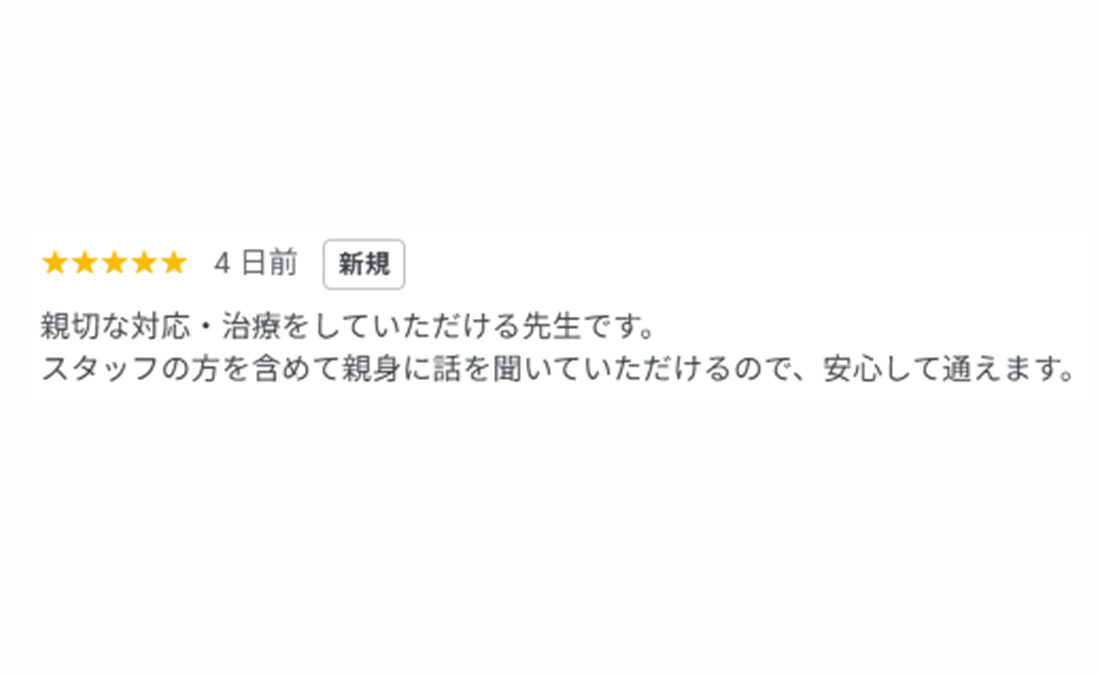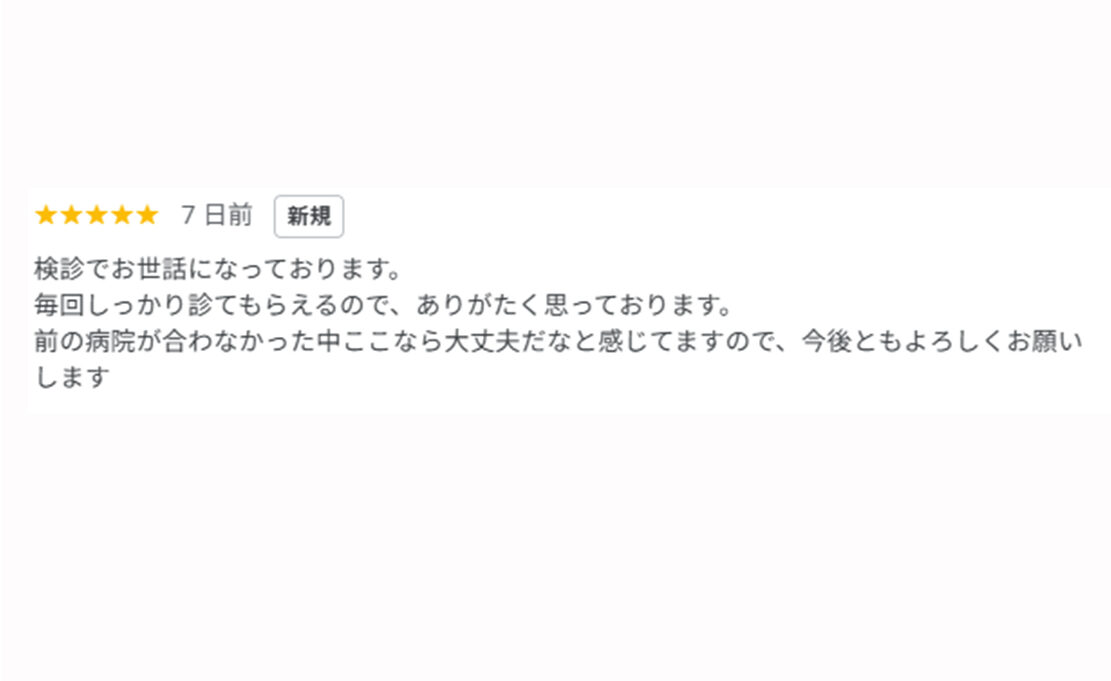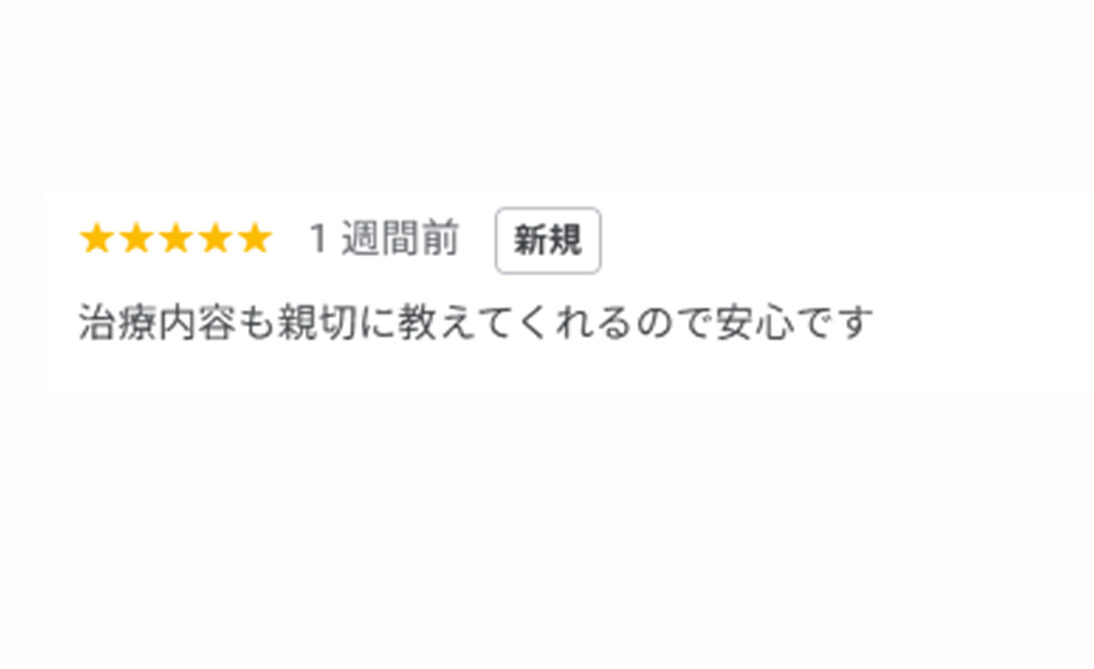インプラント治療は失った歯を補う手段として有効ですが、治療費や手術のリスク、治療後のメンテナンスなど不安が尽きないという方も多いのではないでしょうか。特に「どのインプラントメーカーを選べばいいのか分からない」「一度断られたけれど、メーカーを変えれば治療できる可能性があるのか」といった疑問をお持ちの方は少なくありません。また、インプラント治療が初めての方は何を基準に選べばいいのかイメージが湧きにくいものです。
インプラントメーカーを比較する理由とは?
インプラントは歯科用の医療機器であり、口腔内に入れた後は10年以上の長期間にわたって使い続けるものです。そのため、「使用されるインプラントの品質や特性が将来のメンテナンスや寿命を左右する」といっても過言ではありません。実際、世界には100種類以上のインプラントメーカーが存在し、日本国内でも30種類以上の製品が流通しているといわれています。
メーカーによって設計や製造技術、表面処理などが異なるため、同じインプラント治療でも患者さんの口腔状態や骨質によって相性が変わることがあります。また、引っ越しや転勤などで歯科医院を変える際、流通量やシェアの少ないメーカーだと部品の供給が途絶える可能性もあります。治療後の調整や修理が必要になったときに、対応してくれる医院が限られていると困る場合もあります。
インプラントメーカーを比較して選ぶことは非常に重要です。特に、一度治療を断られた方の場合は、メーカーや治療プランを変えることで治療が可能となる場合もあるため、歯科医院とよく相談して最適な選択肢を検討しましょう。
インプラントメーカー選びでチェックすべき4つのポイント
1. インプラント構造(1ピース型・2ピース型)
インプラントは大きく分けて「1ピース型」と「2ピース型」の2種類があります。
- 1ピース型:インプラント体(人工歯根)とアバットメント(被せ物を支える部品)が一体化したタイプです。主に一回法と呼ばれる手術方法と併用されることが多く、外科手術の回数を減らせるメリットがあります。ただし、部品が一体化しているため、角度調整などの自由度は2ピース型よりも低くなる傾向があります。
- 2ピース型:インプラント体とアバットメントが分離しており、術後にアバットメントの取り換えや修理がしやすいのが特徴です。角度の微調整が可能で、骨量や骨質がさまざまな症例に対応しやすく、多くの医院で採用されています。
1ピース型か2ピース型かはメーカーによってラインナップが異なるため、まずは担当の歯科医師がどちらを使っているのか確認してみましょう。手術回数を減らしたい方や、治療期間を短縮したい方には1ピース型が選ばれる場合もあります。一方で、多様な口腔環境や将来的な部品交換をする場合は2ピース型が検討されることが多いです。
2. 基本的な材料
インプラントの素材は、チタンやチタン合金などの金属が主に使われています。チタンは軽量で身体との親和性が高く、骨としっかり結合しやすい特性を持つため、医療用材料として長く信頼されています。メーカーによってはチタン合金やチタン・ニッケル合金を採用しており、さらに強度や腐食耐性を高めているところもあります。
素材面で大きな差は感じにくいかもしれませんが、合金の種類によっては骨との結合速度や強度に若干の違いが出ることもあります。とはいえ、「品質管理の行き届いた大手メーカー製チタンインプラントは、いずれも身体との親和性が高く、耐久性を持っている」のが一般的です。
3. 表面処理技術
インプラントの表面処理は、インプラント体と骨がよりスムーズに結合するかどうかを左右する要素です。主な表面処理として、以下のようなものがあります。
- ブラスト処理:細かい粒子を吹き付けて表面を荒らす処理。骨との密着度を高め、初期結合を促進します。
- 酸処理:ブラストで付着した粒子や不純物を洗浄し、清潔かつ適度に粗面化した表面を維持する方法です。
- 酸化処理:表面を酸化させることで凹凸を増やし、骨細胞がインプラント表面に付着しやすくなるよう工夫されています。
- 機械研磨処理:表面を平滑に整える処理で、歯周組織への影響を抑えたい場合などに使われることがあります。
メーカーによっては、独自に特許を取得した表面処理技術を採用していることもあり、その分、骨結合の速度や安定性に差が出るとされています。
4. 形状
インプラントの外形には以下のタイプがあります。
- スクリュータイプ:ネジ型の形状。表面積が大きくなるため骨との結合が良好で、幅広い症例に対応できます。
- シリンダータイプ:円柱状の形状。スクリュータイプに比べると骨との機械的固定力は劣る場合がありますが、適切な骨量がある症例で用いられることがあります。
- バスケットタイプ:現在ではあまり使われない形状。骨欠損が大きい部位など、特殊な症例で一部の医院が採用している程度です。
- ブレードタイプ:平たいブレード状の形状で、これも現在ではほとんど使われていません。
多くのメーカーはスクリュータイプやシリンダータイプを主力製品としています。患者さんが実際に選ぶ際には、形状そのものよりも、歯科医師が骨の状態に合わせてどの形を選ぶかが重要になります。「治療を行う医師の経験と知識が、最適な形状を判断するカギ」ですので、信頼できる医院で相談することが大切です。
主要インプラントメーカー4社の特徴
日本国内でも広く使用されている主要なインプラントメーカー4社(ストローマン、ノーベルバイオケア、ジンヴィ、アストラテック)の特徴を紹介します。それぞれのメーカーに強みがあるため、実績やアフターフォロー体制なども含めた検討が必要です。
1. ストローマン(スイス)
世界トップクラスのシェアを誇るメーカーで、国際インプラント学会(ITI)と連携した研究開発体制が魅力の一つです。長年にわたる豊富な臨床データを基に、独自の表面処理技術を進化させてきました。骨結合のスピードと安定性に優れ、「初期段階からしっかりと定着し、長期的に安定した実績を持っている」点が多くの歯科医師から高い評価を得ています。また、世界的なシェアの高さから転居時にも対応医院が見つかりやすいのもメリットです。
2. ノーベルバイオケア(スウェーデン発祥・スイス本社)
ブローネマルク教授が開発したインプラントシステムをもととする老舗メーカーで、最も長い歴史と豊富な症例数を持つと言われています。現在はスイスに本社を置き、世界中で製品展開を行っています。部品の継続した供給体制が整っているため、古いシステムを使用していてもパーツ交換が可能な場合が多いメリットがあります。表面処理技術やアバットメントの種類が豊富で、多様な症例に柔軟に対応できる点も魅力です。
3. ジンヴィ(Zimmer Biomet / アメリカ)
アメリカを拠点とするメーカーで、難しい症例に対応しやすい製品ラインナップや、骨結合を高める独自技術に定評があります。特に骨が薄い場合や骨質が十分でない場合でも、インプラントが入れやすいように設計されたシステムがあるため、「一度治療を断られた方がジンヴィ製品で治療可能となる場合」もあります。アメリカでのシェアが高いため、海外との往来が多い方などにはアフターフォローの面で安心感があるといえるでしょう。
4. アストラテック(スウェーデン)
スウェーデンの大手企業グループに属し、公的機関との共同研究を通じて高精度のインプラントを生み出しているメーカーです。表面処理技術に特徴があり、早期の骨結合と長期的な安定性を両立させることを目指しています。審美性と機能性のバランスが良く、特に前歯など見た目を重視する部位での使用実績も豊富です。国内でも取り扱い医院も増えており、安定した部品供給体制が整備されつつあります。
メーカー選びの注意点とアフターサービスの重要性
メーカーの違いは主に製品の信頼性や表面処理技術、部品供給の安定性などにみられますが、実際に患者さんにとって大切なのは「長期的に安心して使い続けられるかどうか」です。インプラントは入れたら終わりではなく、その後のメンテナンスが欠かせません。特に、以下の点は必ず確認しておきましょう。
- 長期的な部品供給:世界的にシェアを持つメーカーほど、転勤・引っ越し先でも対応医院を見つけやすく、部品交換が必要になった際もスムーズに手配できます。
- メンテナンスのしやすさ:歯科医院の経験や扱い慣れなどによって、インプラントの清掃やケアのしやすさが変わります。対応しやすいメーカーを選ぶとトラブルにも早期に対応できます。
- メーカー保証・医院独自の保証制度:メーカーが定める保証だけでなく、医院独自の保証制度が充実しているかどうかも大切な判断材料です。
インプラントメーカー比較の実際:料金と長期的なコストパフォーマンス
「大手メーカーは高額だけど、本当に費用に見合う価値があるの?」と疑問を抱く方もいるでしょう。確かに大手メーカーのインプラントは比較的高価になります。しかし、長期的な視点でみると、部品の安定供給や高い生存率によって再手術や再治療のリスクが減るため、コストパフォーマンスが高くなる可能性があります。
一方、比較的新しいメーカーや安価な海外製を選ぶ場合、初期費用は抑えられるかもしれませんが、メーカーが撤退したり部品が製造中止になったりするリスクもあります。再治療が必要になった場合、その費用や身体的負担は小さくありません。長期的な安心感を重視するなら、大手メーカーや実績あるメーカーを選ぶのが無難です。
歯科医院選びも重要:術者の技術と経験
インプラントメーカーを比較検討することは大切ですが、「最終的には、治療を行う歯科医師の技術と経験が成功率を大きく左右する」ことを忘れてはいけません。いくら高品質のインプラントを使っても、歯科医師のスキルが伴わなければ満足のいく結果は得られないからです。
特に、「骨量が足りない」「骨質が悪い」などの理由でインプラント治療を断られた方は、難しい症例への対応実績が豊富な歯科医院を探すことがポイントです。サイナスリフトやGBR(骨再生療法)など、骨を増やす補助手術ができるかどうかも確認しておきましょう。また、歯科医院によって得意とするメーカーや扱っているメーカーの種類が異なるため、カウンセリング時にしっかり質問してみると安心です。
症例別に見るインプラントメーカーの選び方
| 症例 | ポイント | おすすめ傾向 |
|---|---|---|
| 骨量に余裕がある症例 | 比較的どのメーカーでも問題なく治療可能。 表面処理技術や生存率、費用を重視して検討。 |
ストローマン、ノーベルバイオケア、アストラテックなど 大手メーカーでの安定した運用が人気。 |
| 骨量が少ない・骨質が弱い症例 | インプラントの形状や表面処理がより重要。 短いインプラントや角度を工夫できるシステムを検討。 |
ジンヴィなど難症例対応の実績があるメーカーや、 骨増成治療と併用できるシステム。 |
| 前歯などの審美部位 | 色味や歯肉との調和、形状が重要。 透明感や自然な見た目を追求。 |
アストラテックの審美ラインや、 審美性に配慮したメーカーの製品が人気。 |
これらはあくまでも一般的な傾向であり、実際は患者さんの口腔環境や歯科医院の方針などの要素を考慮して決定します。特に骨量不足で難しい症例とされている方は、「必ずしもメーカーの選択だけで解決できるわけではない」ため、骨増生を伴う治療に熟練した医院を選ぶことが不可欠です。
まとめ
インプラントメーカーの違いは、構造・表面処理・形状・材料・アフターサービスなど多岐にわたります。大きなメーカーであればあるほど、長期使用に耐えうる臨床データと部品供給の安定性を備えているため、将来的な安心感が得られるでしょう。一方、特殊な症例や骨量不足などの場合、新しいメーカーの製品が適している場合もあります。
最も大切なのは「自分の口腔状態やライフスタイルに合わせて、最適なメーカーと治療プランを選ぶこと」です。そして、それを実現してくれる歯科医院の技術と経験、アフターケア体制が重要です。インプラント治療は高額な投資だからこそ、一度カウンセリングを受けてから複数の医院を比較検討するのがおすすめです。
もし一度インプラント治療を断られた方や、不安が大きく決断できない方も、決してあきらめずに治療を検討してみてください。骨増生治療をはじめ技術は日々進歩しており、以前は難しかった症例でも治療可能になっている場合は少なくありません。「インプラントメーカー選び」と「信頼できる歯科医院選び」の両方に目を向け、最善の治療法を見つけていただければ幸いです。
日本歯科札幌では、豊富な治療実績と先端の技術力を活かし、患者さまの希望に沿ったオーダーメイドのインプラント治療を提供しています。専門スタッフのチーム医療と充実したサポート体制で、術前の疑問や不安をしっかりと解消しながら、安全・安心の治療を目指します。まずはお気軽にご相談ください。