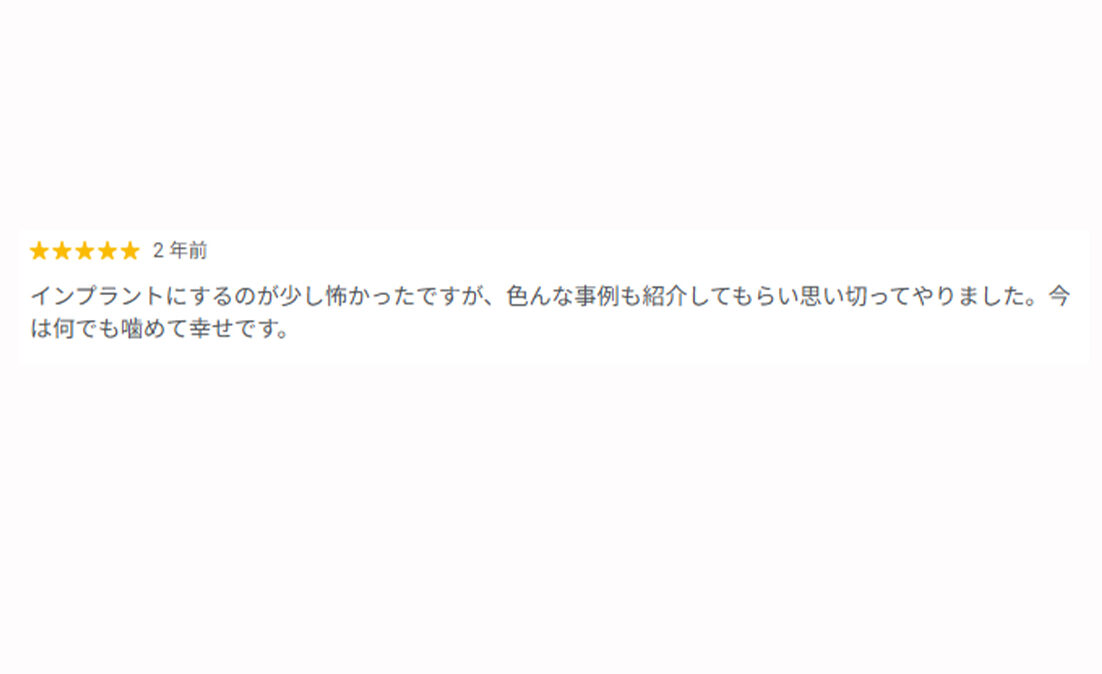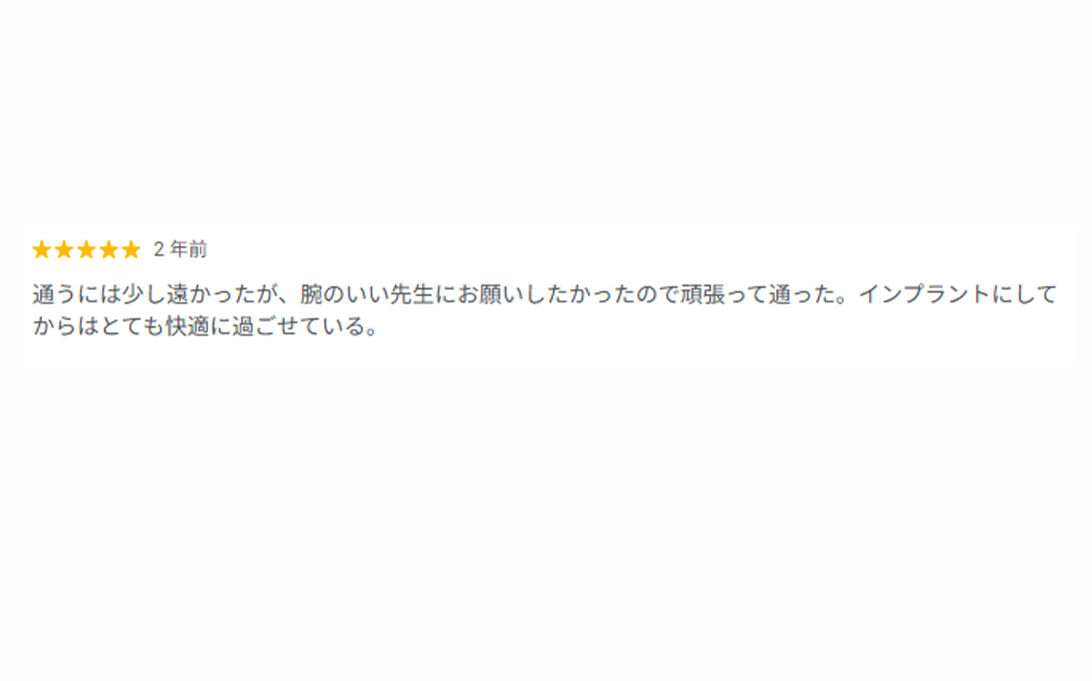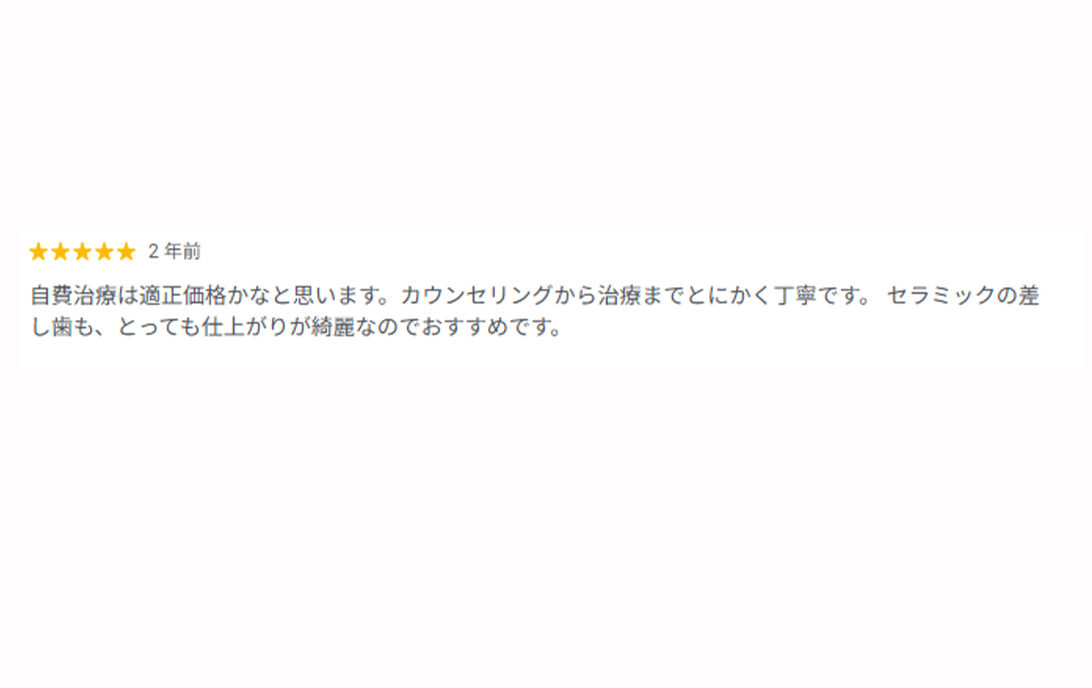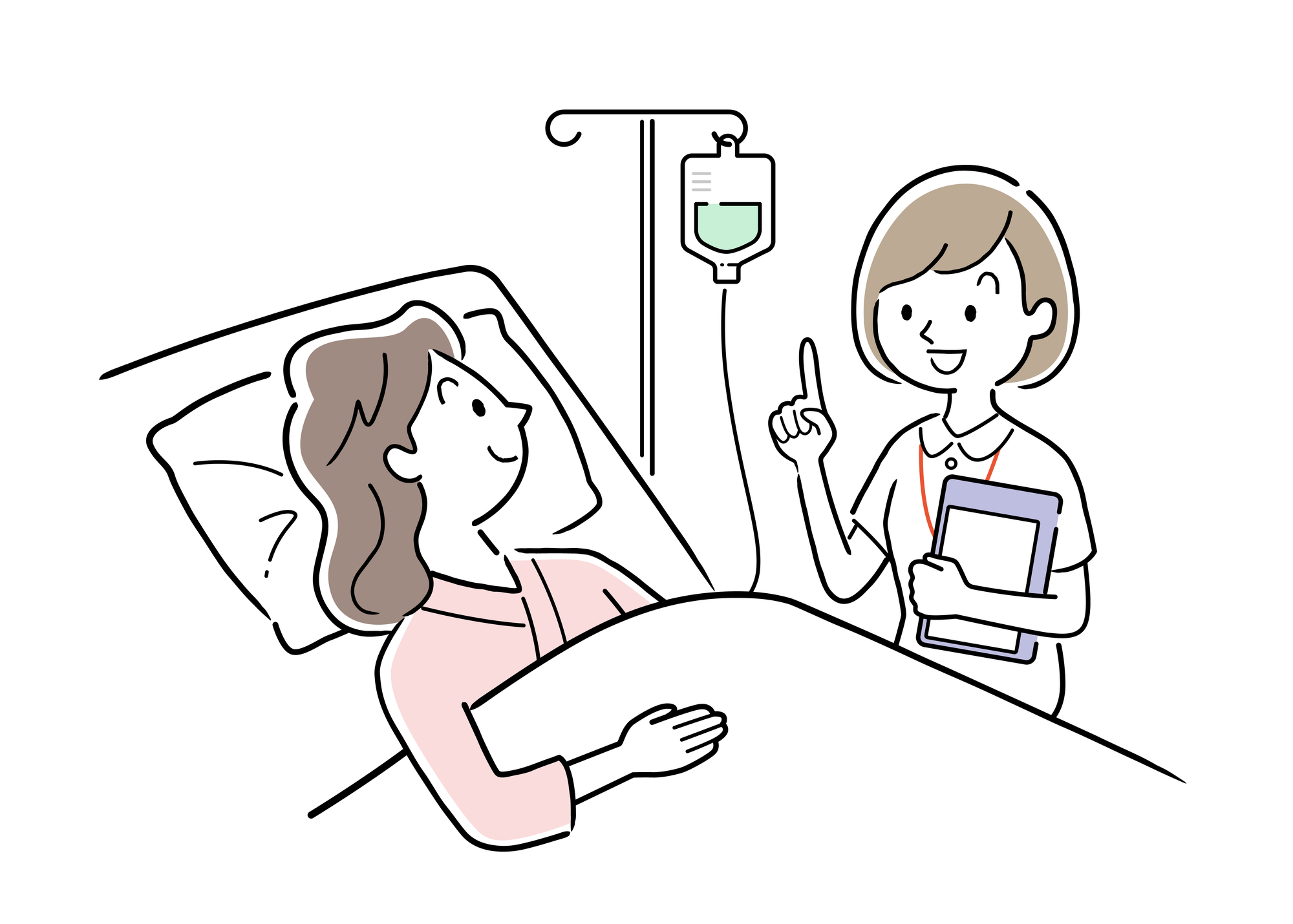
外科矯正は、歯並びを整えるだけでなく、顎骨の位置異常を外科手術で改善し、審美面や機能面で大きな変化が期待できる治療法です。一般的な矯正治療で対応しきれない重度の受け口や出っ歯、顎のズレなどを根本的に解消できますが、全身麻酔を用いた手術が必要なため、治療のハードルが高いと感じる方も多いかもしれません。この記事では、外科矯正によって得られる効果や治療の流れ、想定されるリスク・副作用、保険適用の仕組みなどを分かりやすく解説していきます。外科矯正を検討中の方や、顎の骨格的な問題に悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。
外科矯正とは
外科矯正は、歯列矯正と外科手術を組み合わせて行う治療法です。通常の矯正治療では、ブラケットやワイヤーなどを用いて歯の位置を動かし、噛み合わせを改善していきます。しかし、顎の骨格に大きなズレがある場合(顎変形症)、歯を動かすだけでは理想的な噛み合わせや顔貌を実現することが難しくなります。このようなケースでは、手術で顎骨を切り、前後・左右などに適切に移動させた後、矯正治療で微調整を行い、噛み合わせや顔立ちのバランスも改善できます。
顎変形症には、下顎が前に出過ぎる「下顎前突(受け口)」、上顎が前に突出している「上顎前突(出っ歯)」、左右非対称に顎がずれている「顔面非対称」など、さまざまなタイプがあります。こうした骨格的なズレを最適な位置に整えることで、咀嚼や発音が改善され、結果的に生活の質が向上するケースも少なくありません。
外科矯正で得られる主な効果
外科矯正は、歯の見た目だけでなく、顎の骨格を理想的な位置に移動させるため、長期的かつ本質的な効果が期待できます。具体的には、以下のようなメリットが挙げられます。
- 噛み合わせを改善し、食物をしっかり噛むことができるようになる
- 顎関節の負担が軽減され、顎関節症や肩こりなどの症状を和らげる可能性がある
- 横顔や正面からの顔立ちが整い、顔貌のバランスが向上する
- 発音がしやすくなり、口腔機能全般が向上する
外科矯正は噛み合わせだけでなく、顔のバランス改善や口元の機能向上にも大きく貢献する包括的な治療法です。骨格に問題がある方にとっては、矯正装置だけで治療するよりも明確な改善が期待できます。
外科矯正の基本的な流れ
外科矯正は、次のようなステップを踏んで進めていきます。治療期間には個人差がありますが、1年半から3年以上かかることが多く、長期的な計画を立てて臨むことが求められます。
術前矯正
まず、外科手術に入る前に、ブラケットやワイヤーを使って歯並びを整える期間があります。これを「術前矯正」と呼び、歯列の凸凹を改善したり、上顎と下顎の幅を合わせたり、前歯の向きを正しい位置に近づけたりする工程です。おおよそ1~2年ほどかけて、術後に適した歯列状態を作り上げます。
外科手術
術前矯正が終了し、手術計画がしっかりと立てられた段階で、入院し、全身麻酔による外科手術が行われます。顎の骨を切開し、前後・上下・左右などの方向に位置を移動させた後、金属プレートなどで固定します。手術は多くの場合、口の中から行われるため、外側に目立つ傷が残らないというメリットがあります。入院期間は1~2週間ほどが一般的です。
下顎のみを手術する場合や、上下顎両方の骨を同時に移動する場合など、症例に応じて手術方法が選ばれます。顎変形症に特化した専門医が執刀するため、安全面や技術面において慎重に計画が進められます。
術後矯正
外科手術で骨格の位置調整を行った後、「術後矯正」に移行します。術前矯正で十分に修正できなかった細かい噛み合わせを整えたり、手術後の顎の位置に合わせて歯並びを微調整したりします。6か月から1年程度かけて、理想的な咬合を完成させます。
保定期間
術後矯正が終了した後、きれいになった歯列や顎の位置が後戻りしないように、「リテーナー(保定装置)」を装着する保定期間に入ります。ここでしっかり保定を行うことが、治療効果を長期間維持するための重要なポイントとなります。
外科矯正が適用されやすい症例
外科矯正が必要となるのは、歯の位置だけでは改善が難しいほど骨格に問題がある場合です。代表的な例として、以下の症例が該当します。
下顎前突(受け口)
下顎が前に大きく突出し、口を閉じたときに下の前歯が上の前歯よりも前にある状態です。噛み合わせが逆になるだけでなく、横顔のバランスが崩れるため、美容面や機能面で大きな問題となることがあります。
上顎前突(出っ歯)
上顎が前に張り出している、または下顎が小さいために相対的に上顎が前に見えるケースです。発音や咀嚼だけでなく、口元が閉じにくい・唇が乾きやすいなどのトラブルを併発することもあります。
顔面の非対称
左右の顎の位置がずれているため、正面から見ると上下顎が傾いたり、歯列がゆがんだりします。顎の歪みが気になる方が多く、放置すると顎関節への負担が左右差により高まることがあります。
外科矯正におけるリスク・副作用
外科矯正は、一般的な矯正治療に比べて大掛かりであり、リスクや副作用が多岐にわたります。主なリスクは以下の通りです。
- 手術後の腫れや痛み、内出血
- 全身麻酔に伴うリスク(合併症など)
- 顎の神経を傷つけることによる麻痺や感覚異常
- 後戻り(手術後、顎がわずかに元の位置に戻る可能性)
- 矯正装置による歯肉退縮や歯根吸収
特に下顎管の神経麻痺や後戻りのリスクは、術前の検査と診断で十分に考慮されますが、完全には回避できません。担当医と十分に相談し、リスクとメリットを天秤にかけて治療方針を決定することが大切です。
外科矯正と保険適用について
顎変形症(手術を伴う矯正治療)は、認可を受けた医療機関で行う場合に保険適用が認められています。すべての医院で保険が適用されるわけではなく、自立支援医療機関や顎口腔機能診断施設など、指定を受けた機関のみで保険診療が可能です。保険適用の範囲内であれば、自己負担割合によって治療費が変わり、限度額を超えた分は「高額療養費制度」を利用して還付を受けることができます。
高額療養費制度の活用
限度額を超えた分は「高額療養費制度」を利用して還付を受けることができます。収入や加入している保険の種類によって自己負担額は変動しますが、月収がそれほど高くない方であれば、実質的な費用負担を軽減できることが多いです。
費用を抑えるためのポイント
外科矯正の費用負担をできるだけ抑えるためには、以下のポイントに留意することが重要です。
| 番号 | ポイント |
|---|---|
| 1 | 保険適用のある医療機関を選ぶ |
| 2 | 高額療養費制度の申請を行う |
| 3 | 事前に治療期間や保険適用範囲をしっかり確認する |
認可を受けたクリニックでは、術前・術後の矯正費用や外科手術費が保険診療の対象となり、3割負担の方は数十万円程度の自己負担で済むことが多いです(症例や収入状況によって異なります)。
外科矯正を受ける際の注意点
外科矯正は長期間の治療が必要なため、以下の点を意識しておくことでスムーズに進めることができます。
- 治療前のカウンセリングでリスクや費用面を十分に確認する
- 食生活や口腔ケアを見直し、むし歯や歯周病のリスクを減らす
- 術後の腫れや痛みに備え、仕事や学校を休む期間を確保する
- 保定期間をきちんと守り、後戻りを防ぐ
また、医療機関によって治療方針や得意とする症例が異なります。他の病院と比較検討するセカンドオピニオンも取り入れ、最適な治療先をじっくり考えて決定しましょう。
まとめ
外科矯正は、顎変形症などの骨格的な問題を抱える方にとって、噛み合わせだけでなく、見た目や機能面でも大きな改善が期待できる治療法です。とはいえ、全身麻酔による手術や長期的な矯正期間が必要なため、費用やリスクについてはあらかじめ把握しておくことが重要になります。保険適用条件を満たす医院を選び、高額療養費制度を活用することで、経済的負担を大きく軽減できます。治療を検討されている方は、まずカウンセリングを受け、不安や疑問を解消した上で治療を始めることをおすすめします。
静岡歯科では、豊富な治療実績と先端の技術力を活かし、患者さまの希望に沿ったオーダーメイドのマウスピース矯正を提供しています。専門スタッフのチーム医療と充実したサポート体制で、術前の疑問や不安をしっかりと解消しながら、安全・安心の治療を目指します。まずはお気軽にご相談ください。