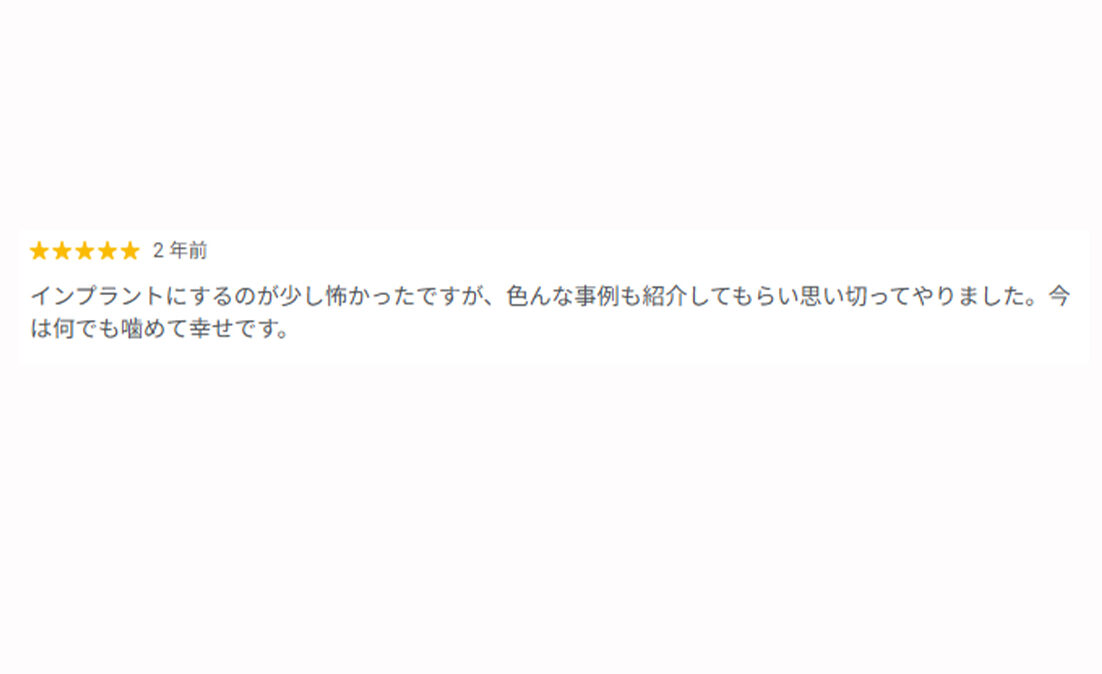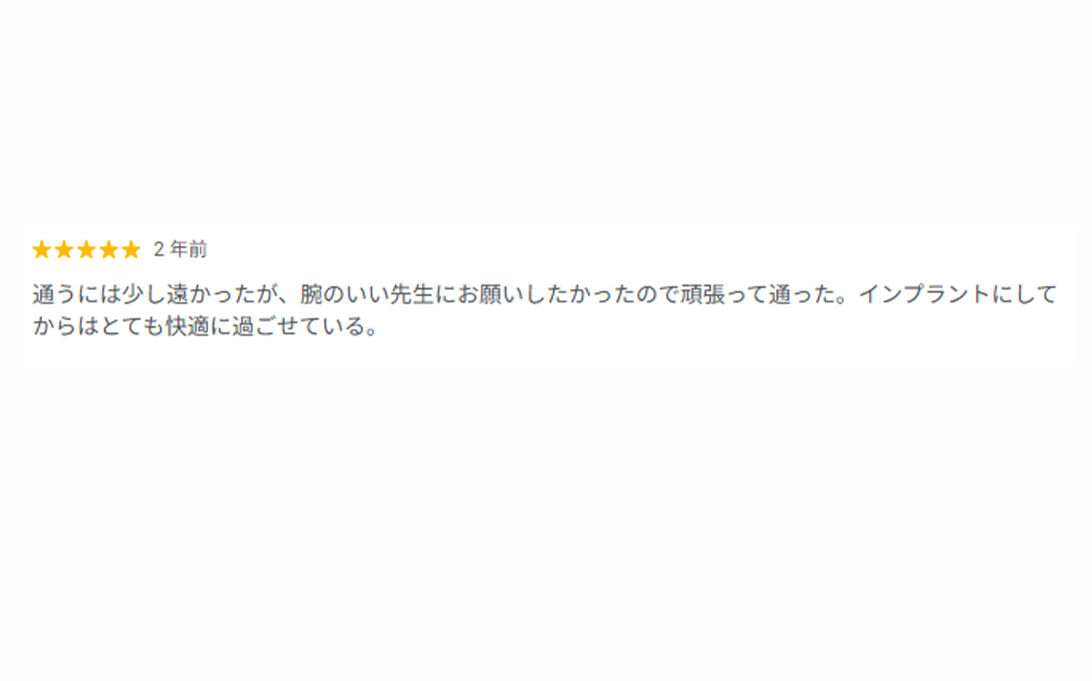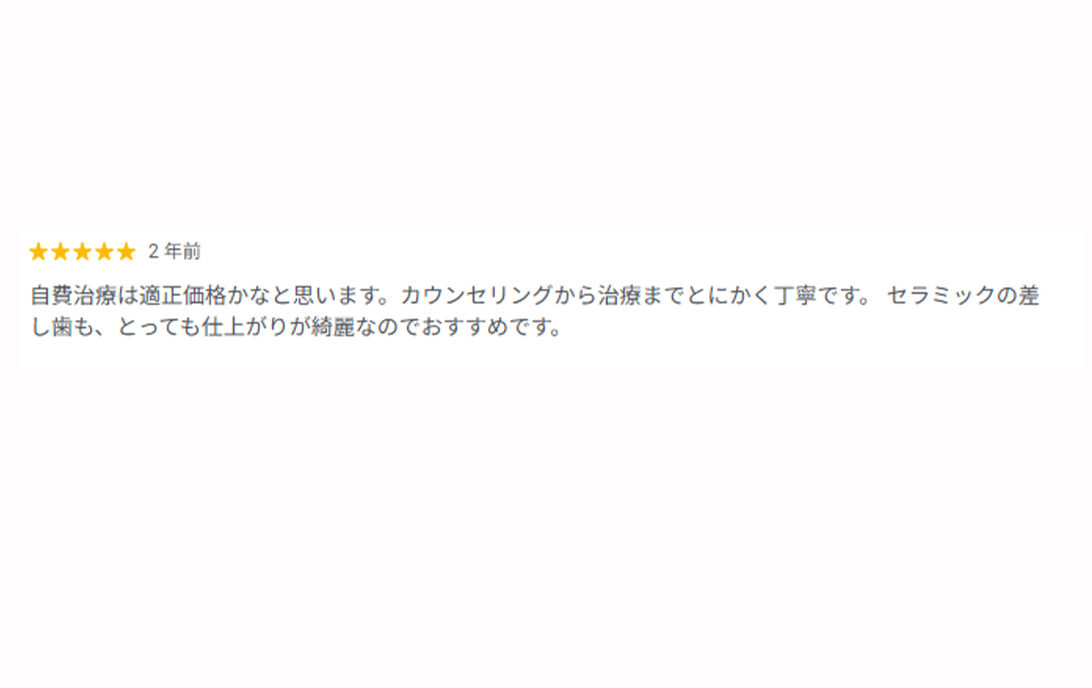歯を失った際の代表的な選択肢であるインプラントやブリッジは、自然な見た目や噛み心地を取り戻せる一方、どちらも適切にケアしないと歯肉や周囲組織へ悪影響を及ぼし、寿命を縮める要因となるため注意が必要です。特に歯と歯肉の境目やブリッジの下部は汚れが溜まりやすく、歯ブラシだけでは十分に清掃できないことも多いのです。
そこで有用なのが「デンタルフロス」です。インプラントやブリッジ周辺は汚れがたまりやすい部分が多いため、念入りなセルフケアが欠かせません。
インプラントの特徴とリスク
インプラントは歯を失った部分の顎の骨に、チタンなど金属製の人工歯根を埋め込み、その上に人工の歯を装着する治療法です。インプラントは歯根がチタンなどの金属製であるため、天然歯に備わった「歯根膜」がありません。
この構造上、汚れが付着すると歯肉が守られにくくなり、人工歯根の周囲に汚れが残ると、インプラント周囲炎を引き起こすリスクが高まります。初期段階では痛みなどの自覚症状が乏しく、気づいたときには症状が進行しているケースも珍しくありません。進行すると歯槽骨が減少してインプラントを支えられなくなるおそれがあります。
そのため、早期発見・早期対処がとても大切です。
ブリッジの特徴とリスク
ブリッジは、欠損している歯の両隣にある支台歯を削って被せ物(連結冠)を作り、失った部分を補う治療法です。見た目や噛み合わせが自然に仕上がるメリットがある一方、連結されたダミーの歯(ポンティック)の下部は通路状になりやすく、歯ブラシだけでは汚れを落としづらいという難点があります。
もし汚れをしっかり落とせないと、ケアを怠ると虫歯や歯周病が進行し、支台となる歯が深刻なダメージを受ける恐れがあります。ブリッジを長く使い続けるためにも、毎日のこまめなケアが欠かせません。
フロスの種類と選び方
インプラントやブリッジのケアにフロスを使用することは非常に効果的です。しかし、フロスにはさまざまな種類があり、それぞれの特性に合わせて使うことが重要です。ここでは、フロスの分類方法についていくつかの観点から解説します。主な分類基準として、使い方、素材、機能性などがあり、これらに基づいてフロスの特徴を紹介します。
形状による分類
フロスは形状によっても大きく分類されます。ホルダータイプと糸巻きタイプは、使い方や操作感が異なるため、個々の使いやすさに合わせて選ぶことができます。
| タイプ | 特徴 |
|---|---|
| ホルダータイプ | 柄に糸が張ってあるため、使い始めのハードルが低く操作しやすい。 |
| 糸巻きタイプ | 自由に糸の長さを調整できるため、慣れれば歯と歯の間を多方向から掃除しやすい。 |
ワックス加工の有無による分類
フロスの糸は、ワックス加工の有無によってさらに分類できます。ワックスタイプは、糸が滑りやすく、狭い歯間でも通しやすいという特徴があります。アンワックスタイプは、糸がプラークをしっかりと絡め取る力が強くなりますが、歯間が狭い場合には切れやすいこともあります。
| タイプ | 特徴 |
|---|---|
| ワックスタイプ | 糸にワックス加工が施されており、狭い歯間にも通しやすい。 |
| アンワックスタイプ | ワックス加工がないぶん、プラークをしっかり絡め取る力が強いが、歯と歯の間が狭いと切れやすい場合がある。 |
機能性による分類
インプラントやブリッジを装着している場合、被せ物との間が狭いケースが多くあります。一方で、歯間が広めな方やブリッジ下部をしっかり掃除したい方には、水分を含むと糸が太くなるタイプなどが適している場合もあります。
| タイプ | 特徴 |
|---|---|
| 膨張タイプ | 唾液や水分を含むと糸が膨らみ、プラークを効率的に絡め取る。 |
| 特殊素材タイプ | ナイロン・ポリエステル・ポリエチレンなど素材に工夫を凝らした製品も豊富に販売されている。 |
インプラント向けのフロスケア
インプラント周囲は天然歯よりも防御力が低く、汚れが残ると周囲炎を起こしやすい部分です。フロスを正しく使い、必要に応じて歯科医院でもメンテナンスを受けましょう。
フロスの基本的な使い方
糸の準備として、糸巻きタイプの場合は30~40cmほどカットし、両手の中指に巻いて15cmほど引っ張れる状態にします。挿入時は、いきなり強く押し込まず、左右に細かく動かしながらゆっくりと挿入しましょう。
歯と歯が密接していて入りづらい場合は、角度を調整しながら少しずつ糸を動かすとスムーズに進みます。除去時は、インプラントやブリッジの境目にしっかりと糸を当て、プラークを丁寧に取り除きましょう。
使用する際は力を入れすぎず、優しいタッチを心がけてください。フロスを抜く際は再度左右に細かく動かしながら、ゆっくりと糸を引き上げてください。
定期検診との併用
インプラントの場合はセルフケアだけでなく、歯科医院での定期的な検診・クリーニングが欠かせません。インプラントやブリッジを長く維持するためには、セルフケアと歯科医院でのプロフェッショナルケアが重要な両輪となります。
ブリッジ向けのフロスケア
ブリッジは欠損歯の代わりになるダミーを含むため、その下部の清掃がとくに大切です。歯ブラシが届きにくいダミー部分の下に食べかすやプラークが溜まると、支台となる歯にまで悪影響を及ぼします。
通しづらい箇所への対応
フロススレッダーやスーパーフロスの活用については、そのような際に「フロススレッダー」や「スーパーフロス」などの補助アイテムが便利です。これらのアイテムを使用すると、フロスを通しやすくなり、汚れを効率よく除去できます。
毎日のケアと定期検診
日々のフロスケアについては、毎日の歯磨き後にはフロスを併用し、できるだけ汚れを落とすことがインプラントやブリッジを長持ちさせるポイントです。とくに就寝前は唾液量が減り、細菌が繁殖しやすいタイミングです。また、プロの目による点検も重要です。セルフケアを熱心に行っていても、専門家の視点から見ると磨き残しがあったり、気づかないうちに歯肉が炎症を起こしている場合があります。
小さなトラブルでも早期に発見・対処することで、大がかりな再治療を回避できるでしょう。
まとめ
インプラントやブリッジのケア不足は、深刻な口腔トラブルを引き起こす可能性があります。インプラント周囲炎による痛みや出血、支台歯の虫歯、口臭、歯肉の黒ずみなどが代表的な症状です。特に注意すべきは、初期症状が気付きにくく、進行すると歯槽骨の減少や支台歯の損傷により、再治療が困難になる点です。
これらのリスクを防ぐには、日々の丁寧な歯磨きとフロスの使用、そして定期的な歯科検診が不可欠です。不安な点があれば、早めに歯科医院に相談し、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。
静岡歯科では、豊富な治療実績と先端の技術力を活かし、患者さまの希望に沿ったオーダーメイドのインプラント治療を提供しています。専門スタッフのチーム医療と充実したサポート体制で、術前の疑問や不安をしっかりと解消しながら、安全・安心の治療を目指します。まずはお気軽にご相談ください。